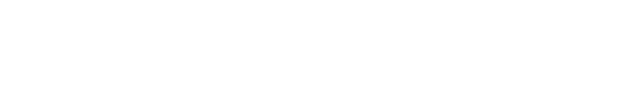虚血性心疾患
虚血性心疾患について知っておきたいこと ~症状、原因から最新治療、Q&Aまで~
「胸が締め付けられるような感じがする」「坂道や階段を上ると息が切れる」といった症状に心当たりはありませんか? もしかしたら、それは「虚血性心疾患」のサインかもしれません。
虚血性心疾患は、日本人の死因の上位を占める心臓病の一つであり、早期発見・早期治療が非常に重要です。このコラムでは、虚血性心疾患とはどのような病気なのか、その症状、原因、検査、治療法について詳しく解説するとともに、当院での対応やよくあるご質問にもお答えします。
Ⅰ.虚血性心疾患とは
虚血性心疾患(きょけつせいしんしっかん)とは、心臓の筋肉(心筋)に酸素や栄養を送る「冠動脈(かんどうみゃく)」という血管が、動脈硬化などによって狭くなったり(狭窄)、詰まってしまったり(閉塞)することで、心筋への血液の流れが悪くなる(虚血)病気の総称です。
心筋が一時的に血液不足になる「狭心症(きょうしんしょう)」と、冠動脈が完全に詰まって心筋が壊死してしまう「心筋梗塞(しんきんこうそく)」が代表的な疾患です。
- 狭心症: 冠動脈が狭くなり、運動時など心臓が多くの酸素を必要とするときに、一時的に心筋への血流が不足する状態です。安静にすると症状が治まることが多いのが特徴です。
- 心筋梗塞: 冠動脈が完全に詰まり、心筋への血流が途絶えてしまう状態です。心筋の細胞が壊死し、命に関わることもある危険な状態です。迅速な治療が必要です。
Ⅱ.虚血性心疾患の初期症状
虚血性心疾患の初期症状は、原因となる疾患や進行度によって異なりますが、以下のような症状が現れることがあります。
- 胸の圧迫感・締め付けられる感じ(胸痛): 最も代表的な症状です。胸の中央部や左胸に感じることが多く、「重い石を乗せられたよう」「万力で締め付けられるよう」と表現されることもあります。
- 胸やけ
- 息切れ・呼吸困難: 特に坂道や階段を上る、重い物を持つなどの労作時に現れやすいです。
- 動悸
- 肩、腕、顎、歯、背中への放散痛: 胸の痛みだけでなく、これらの部位に痛みや違和感として現れることもあります。
- 吐き気・嘔吐
- 冷や汗
- めまい・失神
特に高齢者や糖尿病患者さんでは、典型的な胸痛が出にくく、息切れや吐き気、倦怠感といった症状のみが現れることもあり、「無痛性心筋虚血」と呼ばれることもあります。いつもと違う体調の変化を感じたら、早めに医療機関を受診することが大切です。
III. 虚血性心疾患の予後
虚血性心疾患の予後(病気の経過の見通し)は、疾患の種類(狭心症か心筋梗塞か)、重症度、治療開始のタイミング、そして治療後の生活習慣の改善状況などによって大きく異なります。
- 狭心症: 早期に適切な治療を受け、生活習慣を改善することで、多くの場合、症状をコントロールし、心筋梗塞への進行を予防することが可能です。しかし、放置すると心筋梗塞に移行するリスクが高まります。
- 心筋梗塞: 発症早期に適切な治療(カテーテル治療やバイパス手術など)を受けることで、救命率は大きく向上しました。しかし、一度壊死した心筋は元には戻らないため、心臓の機能が低下し、心不全などの合併症を引き起こす可能性があります。退院後も、再発予防のための薬物療法やリハビリテーション、生活習慣の改善が不可欠です。
いずれの疾患においても、早期発見・早期治療と、その後の継続的な管理が予後を大きく左右します。医師の指示に従い、根気強く治療に取り組むことが重要です。
Ⅳ.虚血性心疾患になる原因
虚血性心疾患の主な原因は「動脈硬化」です。動脈硬化とは、血管の内壁にコレステロールなどの脂質が沈着し、血管が硬く、狭くなる状態を指します。冠動脈に動脈硬化が起こると、血液の流れが悪くなり、虚血性心疾患を引き起こします。
動脈硬化を進行させる主な危険因子(リスクファクター)は以下の通りです。
- 高血圧: 血管に常に高い圧力がかかることで、血管壁が傷つきやすくなり、動脈硬化が進行します。
- 脂質異常症(高コレステロール血症など): 血液中の悪玉コレステロール(LDLコレステロール)や中性脂肪が多いと、血管壁に沈着しやすくなります。
- 糖尿病: 高血糖の状態が続くと、血管が傷つきやすくなり、動脈硬化が進行します。また、糖尿病は神経障害を合併することがあり、胸痛を感じにくくなることもあります。
- 喫煙: タバコに含まれるニコチンや一酸化炭素などが、血管を収縮させたり、血管壁を傷つけたりして動脈硬化を促進します。
- 肥満(特に内臓脂肪型肥満): 肥満は、高血圧、脂質異常症、糖尿病などの危険因子と関連が深いです。
- 運動不足: 運動不足は、肥満や生活習慣病のリスクを高めます。
- ストレス: 慢性的なストレスは、血圧の上昇や血管の収縮を引き起こし、動脈硬化を悪化させる可能性があります。
- 加齢: 年齢とともに動脈硬化は進行しやすくなります。
- 遺伝的要因(家族歴): 血縁者に虚血性心疾患の方がいる場合、発症リスクが高まることがあります。
これらの危険因子が複数重なることで、動脈硬化の進行は加速し、虚血性心疾患の発症リスクがさらに高まります。
Ⅴ.虚血性心疾患の検査方法
虚血性心疾患が疑われる場合、以下のような検査を組み合わせて診断を行います(当院では実施できない項目も含まれています)。
- 問診・診察: 症状、既往歴、家族歴、生活習慣などを詳しく伺います。
- 心電図検査: 心臓の電気的な活動を記録し、心筋虚血や不整脈の有無を調べます。安静時だけでなく、運動負荷時(トレッドミル検査やエルゴメーター検査)に行うことで、狭心症の診断に有用な場合があります。ホルター心電図(24時間心電図)では、日常生活中の心電図変化を捉えることができます。
- 血液検査: 心筋梗塞の際に心筋から漏れ出す酵素(心筋逸脱酵素)や、炎症反応、脂質(コレステロール、中性脂肪)、血糖値などを調べ、危険因子や心筋障害の程度を評価します。
- 胸部X線検査(レントゲン検査): 心臓の大きさや形、肺の状態などを確認します。心不全の合併などを評価するのに役立ちます。
- 心エコー検査(心臓超音波検査): 超音波を使って心臓の形、大きさ、壁の動き、弁の状態、ポンプ機能などをリアルタイムに観察します。心筋虚血による壁運動の異常や、心筋梗塞による心機能低下の評価に非常に有用です。
- 運動負荷心エコー検査・薬物負荷心エコー検査: 運動や薬剤で心臓に負荷をかけながら心エコーを行い、安静時では現れない心筋虚血の兆候を捉えます。
- 冠動脈CT検査: 造影剤を使用して冠動脈を撮影し、血管の狭窄や石灰化の程度を評価します。カテーテル検査に比べて低侵襲で、スクリーニング検査としても用いられます。
- 心臓核医学検査(心筋シンチグラフィ): 微量の放射性同位元素を注射し、心筋への血流分布や心筋の機能を評価します。運動負荷や薬物負荷と組み合わせて行われることもあります。
- 心臓カテーテル検査(冠動脈造影検査): 手首や足の付け根の動脈から細いカテーテルを挿入し、冠動脈まで進めて造影剤を注入し、X線で撮影します。冠動脈の狭窄や閉塞の部位や程度を最も正確に診断できる検査です。必要に応じて、そのまま治療(カテーテルインターベンション)を行うこともあります。
これらの検査を症状や状態に応じて選択し、総合的に診断します。
Ⅵ.虚血性心疾患の治療法
虚血性心疾患の治療は、大きく分けて以下の3つがあります。これらを患者さんの状態や病態に応じて組み合わせて行います。
- 生活習慣の改善: 治療の基本であり、再発予防にも非常に重要です。
- 禁煙: 最も重要な生活習慣の改善です。
- 食事療法: 塩分、脂肪分、コレステロールの摂取を控え、バランスの取れた食事を心がけます。野菜や魚を積極的に摂ることが推奨されます。
- 運動療法: 適度な有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、水泳など)は、血圧や血糖値、脂質異常の改善に繋がり、心臓の機能を高める効果も期待できます。医師の指導のもと、適切な運動量で行うことが大切です。
- 体重管理: 肥満の場合は、適切な体重まで減量します。
- ストレス管理: 十分な睡眠、リラックスできる時間を持つなど、ストレスを溜めない工夫をしましょう。
- 節酒: 過度な飲酒は避けましょう。
- 薬物療法: 症状の緩和、病気の進行抑制、心筋梗塞の予防などを目的に行われます。
- 抗血小板薬: 血液を固まりにくくし、血栓ができるのを防ぎます。(例:アスピリン、クロピドグレルなど)
- 血管拡張薬(硝酸薬など): 冠動脈を広げ、心筋への血流を改善し、胸痛発作を予防・治療します。
- β遮断薬: 心臓の働きを少し休ませ、心拍数や血圧を下げ、心筋の酸素消費量を減らします。
- カルシウム拮抗薬: 冠動脈を拡張させたり、血圧を下げたりします。
- スタチン系薬剤(HMG-CoA還元酵素阻害薬): 悪玉コレステロール(LDLコレステロール)を下げ、動脈硬化の進行を抑えます。
- ACE阻害薬・ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬): 血圧を下げ、心臓を保護する作用があります。
- その他、必要に応じて血糖値を下げる薬、利尿薬などが用いられます。
- カテーテル治療(経皮的冠動脈インターベンション:PCI): 狭窄または閉塞した冠動脈を、カテーテルを用いて内側から広げる治療法です。手首や足の付け根の動脈から細いカテーテルを挿入し、先端に風船(バルーン)や金属の網(ステント)がついたカテーテルを病変部まで進めます。バルーンで血管を拡張したり、ステントを留置して血管を内側から支えたりします。心筋梗塞では、緊急で行われることが多い治療法です。
- 冠動脈バイパス手術(CABG): カテーテル治療が困難な場合や、複数の冠動脈に病変がある場合などに行われる外科手術です。体の他の部位から採取した血管(内胸動脈、橈骨動脈、大伏在静脈など)を使って、狭窄・閉塞した冠動脈の先に新しい血流路(バイパス)を作成します。
どの治療法を選択するかは、患者さんの年齢、全身状態、病変の部位や数、重症度などを総合的に判断して決定されます。
VII. 当院の対応可否
当院では、虚血性心疾患の診断(心電図、心エコー検査、血液検査など)および薬物療法を中心とした治療、生活習慣指導を行っております。冠動脈CT検査や心臓カテーテル検査、カテーテル治療、冠動脈バイパス手術など、より専門的な検査や治療が必要と判断された場合には、連携する高度医療機関へ速やかにご紹介させていただきます。
胸の症状や健康診断で異常を指摘された方、生活習慣病をお持ちで心臓のことが心配な方は、お気軽にご相談ください。
Ⅸ. Q&A (虚血性心疾患に関するよくあるご質問)
患者様からよく寄せられるご質問とその回答をまとめました。
Q1. 虚血性心疾患は治りますか?
A1. 一度動脈硬化で傷んだ血管や、心筋梗塞で壊死してしまった心筋を完全に元通りにすることは難しいのが現状です。しかし、適切な治療と生活習慣の改善により、症状をコントロールし、病気の進行を遅らせ、心筋梗塞などのより重篤な状態への移行を防ぐことは十分に可能です。早期発見・早期治療と、治療後の継続的な自己管理が非常に重要となります。「治す」というよりは、「上手に付き合っていく」という意識で、根気強く治療に取り組むことが大切です。
Q2. 虚血性心疾患と診断されたら、食事で気をつけることは何ですか?
A2. 食事療法は虚血性心疾患の治療と再発予防において非常に重要です。以下の点に注意しましょう。
- 減塩: 塩分の摂りすぎは高血圧の原因となり、心臓に負担をかけます。1日の塩分摂取量を6g未満に抑えるのが目標です。
- 脂質のコントロール: 悪玉コレステロールや中性脂肪を増やす飽和脂肪酸(肉の脂身、バターなど)やトランス脂肪酸(マーガリン、ショートニングなど)の摂取を控え、魚油に多く含まれるEPA・DHAや、オリーブオイルなどの不飽和脂肪酸を適度に摂りましょう。
- コレステロールの多い食品の制限: 卵黄、レバー、魚卵などは食べ過ぎに注意しましょう。
- 食物繊維の積極的な摂取: 野菜、果物、きのこ類、海藻類、豆類などを積極的に摂りましょう。食物繊維はコレステロールの吸収を抑える効果があります。
- 糖質の摂りすぎに注意: 特に糖尿病の方は、血糖コントロールが重要です。
- バランスの取れた食事: 主食、主菜、副菜をバランス良く摂ることが基本です。 具体的な食事内容については、医師や管理栄養士にご相談ください。
Q3. 運動はしても良いのでしょうか?どの程度なら大丈夫ですか?
A3. 虚血性心疾患の患者さんにとって、適度な運動は心臓リハビリテーションの一環として非常に有効です。心肺機能の維持・向上、体力向上、危険因子の改善(血圧、血糖値、脂質のコントロール)、気分の改善などの効果が期待できます。 ただし、病状や体力には個人差があるため、自己判断で運動を始めるのは危険です。必ず医師に相談し、運動の種類、強度、時間、頻度などについて具体的な指示を受けてください。一般的には、ウォーキング、軽いジョギング、自転車、水泳などの有酸素運動が推奨されます。運動中に胸痛や息切れなどの症状が出た場合は、すぐに運動を中止し、医師に相談してください。
Q4. 薬はずっと飲み続けなければなりませんか?
A4. 虚血性心疾患の治療薬の多くは、病気の進行を抑えたり、再発を予防したりするために、長期的に服用を継続する必要があります。例えば、血液をサラサラにする抗血小板薬や、コレステロールを下げるスタチン系薬剤などは、自己判断で中断すると心筋梗塞などのリスクが高まる可能性があります。 症状が改善したように感じても、薬の量や種類を自己判断で変更したり中止したりせず、必ず医師の指示に従ってください。薬に関する疑問や不安がある場合は、遠慮なく医師や薬剤師にご相談ください。
Q5. 虚血性心疾患は遺伝しますか?
A5. 虚血性心疾患そのものが直接的に遺伝するわけではありませんが、「なりやすい体質」が遺伝する可能性はあります。具体的には、高血圧、脂質異常症、糖尿病といった虚血性心疾患の危険因子が遺伝的に起こりやすい家系があります。また、家族歴(血縁者に若くして虚血性心疾患を発症した方がいるなど)は、それ自体が独立した危険因子と考えられています。 ご家族に虚血性心疾患の方がいらっしゃる場合は、ご自身も定期的な健康診断を受け、生活習慣に気をつけるなど、より一層の予防意識を持つことが大切です。
Q6. 胸の痛み以外に、注意すべき症状はありますか?
A6. はい、あります。II章の「虚血性心疾患の初期症状」でも触れましたが、典型的な胸痛だけでなく、以下のような症状にも注意が必要です。
- 肩、腕、顎、歯、背中への放散痛
- 息切れ、呼吸困難(特に労作時)
- 動悸
- 吐き気、嘔吐
- 冷や汗
- めまい、失神
- 原因不明の倦怠感(特に高齢者や糖尿病をお持ちの方は、典型的な胸痛が出にくいことがあります。)
これらの症状が続く場合や、いつもと違うと感じる場合は、早めに循環器内科を受診してください。
Q7. 虚血性心疾患を予防するにはどうすれば良いですか?
A7. 虚血性心疾患の最大の原因である動脈硬化を予防・進行を遅らせることが、最も効果的な予防法です。IV章の「虚血性心疾患になる原因」で挙げた危険因子を減らすことが重要になります。
- 禁煙
- バランスの取れた食事(減塩、低脂肪、野菜や魚を多く摂る)
- 適度な運動習慣
- 適正体重の維持
- 十分な睡眠と休養、ストレス管理
- 高血圧、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病の適切な管理(定期的な受診と治療の継続)
- 定期的な健康診断の受診: 健康的な生活習慣を心がけ、危険因子を早期に発見し対策を講じることが、虚血性心疾患の予防に繋がります。
この記事が、皆さまの虚血性心疾患への理解を深め、健康管理の一助となれば幸いです。ご心配な点がございましたら、どうぞお気軽に当院にご相談ください。