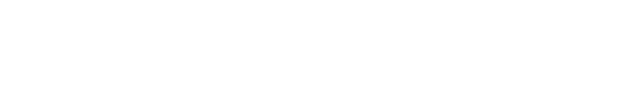狭心症の話
【はじめに】
狭心症は心臓の血管である冠動脈が狭くなる病気です。冠動脈が狭くなると心臓に血液が行きづらくなり、その結果、胸の圧迫感や痛み、動悸などが出現します。
初めは運動したときなど労作時に胸の違和感をおぼえることが多く、徐々にその回数が増していき、最終的には胸の痛みがおさまらなくなります。痛みがおさまらず持続するということは冠動脈がつまった可能性があり(心筋梗塞)、手遅れになることもあり命にも関わります。したがって普段の生活で胸部違和感が続く場合は一度循環器内科に相談してみましょう。
私は血圧の高い方、糖尿病の方、コレステロール値の高い方を外来で診察することが多いのですが、「先生、たいしたことではありませんが、たまに胸が痛いことがあります。すぐおさまっちゃうのですけどね」と言われ、それに加えて「健康診断で異常なしと言われたから大丈夫ですよね?」と聞かれます。
私と致しましては健康診断で大丈夫だったのだから大丈夫ですと言ってあげたいのですが、狭心症に関して言えば、答えは「大丈夫ではありません」です。「すぐおさまっちゃう胸痛が続く!」。これは狭心症を念頭に置けばたいしたことなのです。狭心症の発作は数分でおさまってしまうことが多く、それが何回も続く。患者さんはすぐおさまるのでそんな大げさなものではないと考えてしまうのです。
また狭心症の痛みは数時間痛みが周期的によくなったり悪くなったりすることはあっても、ずっと痛みが数時間「続きっぱなし」ということはあまりありません。またチクチクする痛みや刺されるような痛みではなく、どちらかといえば重苦しい違和感を訴える患者さんが多いです。
狭心症は健康診断でのレントゲン検査、心電図、血液検査ではわかりません。なぜなら狭心症の原因である冠動脈の狭窄は通常のレントゲン検査で見えることはないからです。冠動脈自体(例外を除いて)レントゲン検査で見えることはありません。また心電図でも異常が出るのは狭心症の発作が出現しているときで、発作が出現していない時の心電図は正常の場合が多いのです。血液検査も正常であることが多く狭心症はわかりません。血液検査で異常が出た場合、もはや狭心症ではなく心筋梗塞(冠動脈がつまった病気)になっている場合が多く命の危険を伴います。
冠動脈がつまる前の狭心症と冠動脈がつまった後の心筋梗塞ではその後の生活に大きな差が出ます。心筋梗塞に関して言えばその後の生活がないかもしれません。命が助かったとしても心臓に後遺症を残すことが少なくありません。狭心症や心筋梗塞の治療は時間との勝負なのです。狭心症は治療してしまえば薬を飲みながら普通に生活ができるようになることが多いです。ちょっとした胸部違和感でも回数が頻回であれば手遅れになる前に循環器内科を受診しましょう。
狭心症について、より詳細を知りたい方は下記にて各項目にまとめておりますので合わせてご覧いただけますと幸甚に存じます。
わらび錦町内科 院長 山本真
Ⅰ.狭心症とは
狭心症は、心臓の筋肉(心筋)に酸素と栄養を送る「冠動脈(かんどうみゃく)」という血管が、動脈硬化などによって狭くなったり、一時的に痙攣(けいれん)したりすることで血流が悪くなり、心筋が一時的に酸素不足に陥る病気です。 これにより、胸の痛みや圧迫感などの症状が現れます。多くの場合、症状は数分から長くても15分程度で治まりますが、心臓からの重要な警告サインと捉えるべきです。
狭心症にはいくつかのタイプがあります。
- 労作性狭心症(ろうさせいきょうしんしょう): 運動や興奮など、心臓に負担がかかった時に症状が現れます。冠動脈の動脈硬化が主な原因です。
- 不安定狭心症(ふあんていきょうしんしょう): 労作に関わらず、安静時にも症状が現れたり、症状が徐々に悪化したりする状態です。心筋梗塞に移行する危険性が高い危険な状態です。
- 冠攣縮性狭心症(かんれんしゅくせいきょうしんしょう): 冠動脈が一時的に痙攣して狭くなり、血流が悪くなることで起こります。明け方や早朝の安静時に症状が出やすいのが特徴です。
Ⅱ.狭心症の初期症状
狭心症の最も代表的な初期症状は、胸の痛みや圧迫感です。しかし、その感じ方は人によって様々です。
- 典型的な症状:
- 胸の中央部や左胸が締め付けられる、押さえつけられるような痛みや圧迫感
- 胸が焼けるような感じ
- 症状は数分~15分程度で、安静にすると軽快することが多い
- 放散痛(ほうさんつう):
- 左肩、腕、あご、首、背中、みぞおちなどに痛みが広がることもあります。
- その他の症状:
- 息切れ、動悸
- 吐き気、冷や汗
- 歯やのどの痛み(関連痛として現れることがあります)
特に高齢者や糖尿病の患者さんでは、はっきりとした胸痛がなく、息切れや体のだるさ、胃の不快感といった非典型的な症状のみが現れることもあり、注意が必要です。
III. 狭心症の予後
狭心症の予後は、そのタイプ、重症度、基礎疾患の有無、そして治療や生活習慣の改善への取り組み方によって大きく変わります。
- 労作性狭心症: 早期に発見し、適切な治療(薬物療法、生活習慣の改善、必要に応じてカテーテル治療など)を行えば、症状をコントロールし、心筋梗塞への進行を遅らせることが可能です。多くの場合、良好な予後が期待できます。
- 不安定狭心症: 緊急性の高い状態で、速やかに適切な治療を行わないと心筋梗塞を発症するリスクが非常に高くなります。迅速な診断と治療介入が予後を大きく左右します。
- 冠攣縮性狭心症: 適切な薬物治療により発作を予防し、コントロールすることが可能です。ただし、まれに重篤な不整脈や心筋梗塞を引き起こすこともあります。
いずれのタイプであっても、診断後は医師の指示に従い、治療を継続し、生活習慣を見直すことが、良好な予後を保つために不可欠です。放置すれば、心機能の低下や心筋梗塞、突然死のリスクが高まります。
Ⅳ.狭心症になる原因
狭心症の主な原因は、冠動脈の動脈硬化です。動脈硬化とは、血管の壁が厚く硬くなり、内腔が狭くなる状態を指します。これにより、心臓への血流が制限されます。
動脈硬化を進行させる主な危険因子(リスクファクター)は以下の通りです。
- 高血圧: 血管に常に高い圧力がかかり、血管壁を傷つけます。
- 脂質異常症(高コレステロール血症など): 血液中の悪玉コレステロール(LDLコレステロール)が多いと、血管壁にプラーク(粥腫)が蓄積しやすくなります。
- 糖尿病: 高血糖状態が血管内皮細胞を障害し、動脈硬化を促進します。
- 喫煙: タバコに含まれる有害物質が血管を収縮させ、血管壁を傷つけ、血栓をできやすくします。
- 肥満(特に内臓脂肪型肥満): 上記の危険因子を複合的に悪化させます。
- 運動不足: 身体活動の低下は、肥満や他の生活習慣病のリスクを高めます。
- ストレス: 慢性的なストレスは血圧上昇や血管収縮を引き起こすことがあります。
- 加齢: 年齢とともに動脈硬化は進行しやすくなります。
- 家族歴: 血縁者に心臓病の方がいる場合、遺伝的な要因も関与する可能性があります。
また、冠攣縮性狭心症の場合は、冠動脈が一時的に痙攣(スパズム)することが原因で、喫煙やストレス、飲酒などが誘因となることがあります。
Ⅴ.狭心症の検査方法
狭心症が疑われる場合、以下のような検査を組み合わせて診断を行います。
- 問診・診察: 症状(いつ、どんな時に、どのくらいの時間、どのような痛みかなど)、既往歴、家族歴、生活習慣などを詳しくお伺いします。
- 心電図検査: 心臓の電気的な活動を記録します。発作時でない場合は正常なことも多いため、以下の負荷試験やホルター心電図と併用されます。
- 安静時心電図: 診察室で安静にした状態で行います。
- 運動負荷心電図: ベルトコンベアの上を歩いたり、自転車を漕いだりしながら心電図を記録し、心臓に負荷をかけた時の変化を見ます。労作性狭心症の診断に有用です。
- ホルター心電図: 小型軽量の心電計を24時間装着し、日常生活中の心電図変化を記録します。不定期に起こる発作や、夜間・早朝の発作(冠攣縮性狭心症など)の検出に役立ちます。
- 心エコー検査(心臓超音波検査): 超音波を使って心臓の形、大きさ、壁の動き、弁の状態などを観察します。心筋の動きが悪くなっている部分がないか、心肥大の有無などを評価します。
- 血液検査: 脂質(コレステロール、中性脂肪)、血糖値、炎症反応などを調べ、動脈硬化のリスクファクターを評価します。心筋梗塞が疑われる場合は、心筋逸脱酵素(トロポニンなど)も測定します。
- 胸部X線検査: 心臓の大きさや形、肺の状態などを確認します。
- 冠動脈CT検査: 造影剤を使用し、CT撮影によって冠動脈の狭窄や石灰化の程度を詳しく評価できます。外来で行える非侵襲的な検査です。
- 心臓カテーテル検査(冠動脈造影検査): 手首や足の付け根の動脈から細い管(カテーテル)を挿入し、冠動脈まで進めて造影剤を注入し、X線で撮影します。冠動脈の狭窄部位や程度を最も正確に診断できる検査です。必要に応じて、そのまま治療(カテーテルインターベンション)を行うこともあります。この検査は専門の医療機関で行われます。
Ⅵ.狭心症の治療法
狭心症の治療は、症状の緩和、生活の質の向上、そして心筋梗塞などのより重篤な心血管イベントへの進行を防ぐことを目的とします。治療法は主に以下の3つに分けられます。
- 生活習慣の改善: 全ての治療の基本となります。
- 禁煙: 最も重要な項目の一つです。
- 食事療法: 塩分・脂肪分・コレステロールの摂取を控え、バランスの取れた食事を心がけます。
- 運動療法: ウォーキングなどの有酸素運動を、医師の指導のもとで適切に行います。
- 体重管理: 肥満の場合は適正体重を目指します。
- ストレス管理: 十分な睡眠と休息、リラックスできる時間を持つことが大切です。
- 節酒: 過度な飲酒は避けましょう。
- 薬物療法: 症状や状態に応じて、以下のような薬剤が用いられます。
- 抗血小板薬(アスピリンなど): 血液をサラサラにし、血栓ができるのを防ぎます。
- 硝酸薬(ニトログリセリンなど): 冠動脈を拡張させ、心臓への血流を増やし、発作時の症状を和らげます。発作予防にも使われます。
- β遮断薬: 心拍数を抑え、心臓の仕事量を減らすことで、心筋の酸素需要を低下させます。
- カルシウム拮抗薬: 冠動脈を拡張させ、血流を改善します。冠攣縮性狭心症の治療にも有効です。
- スタチン系薬剤: コレステロール値を下げ、動脈硬化の進行を抑えます。
- その他、必要に応じてACE阻害薬やARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)などが用いられることもあります。
- 冠血行再建術 :これらの治療は、薬物療法だけでは効果が不十分な場合や、重症な狭心症の場合に選択されます。
- カテーテル治療(経皮的冠動脈インターベンション:PCI): 手首や足の付け根の動脈からカテーテルを挿入し、狭窄部位を風船(バルーン)で拡張したり、ステントという金属の網状の筒を留置したりして血流を確保します。
- 冠動脈バイパス手術(CABG): 複数の冠動脈に狭窄がある場合や、カテーテル治療が困難な場合に選択されることがあります。体の他の部位から採取した血管(グラフト)を使って、冠動脈の狭窄部分を迂回する新しい血流路(バイパス)を作成する手術です。
治療法の選択は、患者さんの年齢、症状、冠動脈の状態、併存疾患などを総合的に評価し、医師と患者さんが十分に話し合って決定します。
VII. 当院の対応可否
当院では、循環器内科専門医が狭心症の診断から治療、管理まで一貫して対応しております。 上記に挙げた問診、心電図(安静時、ホルター)、心エコー検査、血液検査、胸部X線検査は当院で実施可能です。これらの検査を通じて、狭心症の的確な診断を目指します。 運動負荷心電図や冠動脈CT、心臓カテーテル検査が必要と判断された場合には、連携する高度医療機関へ速やかにご紹介し、検査や治療を受けていただける体制を整えております。
治療に関しては、生活習慣の改善指導、薬物療法を中心に行います。定期的な通院を通じて、症状のコントロール、再発予防、合併症の早期発見に努め、患者様一人ひとりに合わせたきめ細やかなサポートを提供いたします。 胸の症状でお悩みの方は、どうぞお気軽に当院にご相談ください。
Ⅷ. Q&A
ここでは、患者様からよく寄せられる狭心症に関するご質問にお答えします。
Q1: 狭心症は治りますか?
A1: 狭心症の原因である動脈硬化そのものを完全になくすことは難しいですが、適切な治療(薬物療法やカテーテル治療など)と生活習慣の改善により、症状をコントロールし、病気の進行を遅らせ、心筋梗塞などのリスクを大幅に減らすことは可能です。治療を継続し、生活習慣を見直すことで、発作のない快適な生活を送ることを目指します。
Q2: 狭心症の胸の痛みはどれくらい続きますか?
A2: 労作性狭心症の場合、典型的な胸の痛みや圧迫感は、通常2~5分程度、長くても15分以内には治まることが多いです。安静にしたり、ニトログリセリン(舌下錠やスプレー)を使用したりすると速やかに軽快するのが特徴です。もし痛みが30分以上続く場合や、冷や汗を伴うような強い痛みの場合は、心筋梗塞の可能性もあるため、すぐに医療機関を受診するか救急車を呼んでください。
Q3: 狭心症を放置するとどうなりますか?
A3: 狭心症を治療せずに放置すると、動脈硬化が進行し、冠動脈の狭窄がさらに悪化します。これにより、発作の頻度が増えたり、軽い動作でも症状が出たりするようになることがあります。最も危険なのは、不安定狭心症へ移行したり、冠動脈が完全に詰まって心筋梗塞を発症したりすることです。心筋梗塞は心臓の筋肉が壊死してしまうため、命に関わることもあり、後遺症として心不全や不整脈が残ることもあります。早期発見・早期治療が非常に重要です。
Q4: 狭心症と心筋梗塞の違いは何ですか?
A4: 狭心症は、冠動脈の血流が悪くなり、心筋が一時的に酸素不足になる状態です。この酸素不足による胸痛は一時的で、血流が再開すれば心筋のダメージは残りません。 一方、心筋梗塞は、冠動脈が完全に詰まるなどして血流が途絶え、心筋が酸素不足により壊死(えし)してしまう状態です。壊死した心筋は元に戻らないため、心臓の機能が低下し、命に関わる危険な状態です。狭心症は心筋梗塞の前触れとも言えます。
Q5: 狭心症の予防はできますか?
A5: はい、狭心症の最大の原因である動脈硬化を予防・進行を遅らせることで、狭心症の発症リスクを減らすことができます。具体的には、以下の生活習慣が重要です。
* 禁煙
* バランスの取れた食事(塩分・脂肪分控えめ、野菜・魚を積極的に)
* 適度な運動(ウォーキングなど)
* 適正体重の維持 * 十分な睡眠と休息、ストレス管理
* 高血圧、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病の適切な管理
定期的な健康診断を受け、ご自身の体の状態を把握することも予防につながります。
【おわりに】
狭心症へのご理解を深める一助となれば幸いです。 胸の症状や健康に関することでご不安な点がございましたら、どうぞお気軽に当院までご相談ください。