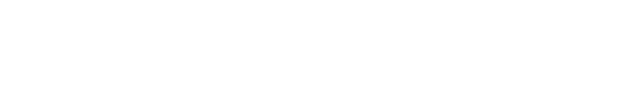高脂血症
「健康診断で脂質の数値が高いと言われた」「コレステロールや中性脂肪が気になる」けれど、具体的にどんな状態なのか、どうすれば良いのか分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、私たちの健康にとって非常に重要な「高脂血症(脂質異常症)」について、その基本から検査、治療法、そして当院での対応まで、分かりやすく解説します
I.高脂血症とは
高脂血症はいわゆる生活習慣病の1つで、血液中の脂質(中性脂肪やコレステロール)が異常に増加する状態をいいます。
従来、高脂血症の診断基準は、
①総コレステロール、悪玉LDLコレステロール、中性脂肪(トリグリセライド)のいずれかの数値が高い
②善玉HDLコレステロールの数値が低い
とされていました。しかし、善玉HDLコレステロールの数値が低いだけで高脂血症と診断するのは不適当であるという理由から、2007年4月に「脂質異常症」に名称が改められました。
脂質異常症は、主に3種類に分類されます。
・高LDLコレステロール血症⇒悪玉LDLコレステロールが多い状態
・低HDLコレステロール血症⇒善玉HDLコレステロールが低い状態
・高トリグリセライド血症⇒中性脂肪(トリグリセライド)が多い状態
高脂血症を長期間放置していると、血管内にコレステロールや中性脂肪(トリグリセライド)が溜まり、血管が詰まってしまう恐れがあります。 症状が進行する前に、生活習慣を見直し早期発見・早期治療をすることが大切です。
II.高脂血症の初期症状
高脂血症の怖いところは、初期にはほとんど自覚症状がないことです。一部、黄色種(まぶたの内側に黄色いしこり)が出現する場合もありますが、一般的には無症状のまま進行します。症状がないからといって放置していると、気づかないうちに血管の中で動脈硬化が進行し、ある日突然、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる病気を引き起こす可能性があります。
そのため、定期的な健康診断などで血液検査を受け、ご自身の脂質の状態を把握しておくことが非常に大切です
III.高脂血症の予後
高脂血症を治療せずに放置すると、以下のような深刻な病気のリスクが高まります。
- 動脈硬化の進行: 血管が硬く、もろくなり、内腔が狭くなります。
- 狭心症・心筋梗塞: 心臓に血液を送る冠動脈が狭くなったり詰まったりすることで起こります。
- 脳梗塞・脳出血: 脳の血管が詰まったり破れたりすることで起こります。
- 閉塞性動脈硬化症: 足の血管が詰まり、歩行時に痛みが出たり、最悪の場合、壊死に至ることもあります。
- 大動脈瘤: 大動脈がこぶのように膨らみ、破裂すると命に関わります。
しかし、早期に発見し、適切な治療(生活習慣の改善や薬物療法)を行うことで、これらの病気のリスクを大幅に減らすことが可能です。医師の指導のもと、根気強く治療を続けることが重要です。
IV.高脂血症になる原因
高脂血症の原因は一つではなく、複数の要因が絡み合っていることが多いです。主な原因としては、以下のものが挙げられます。
-
- 食生活の乱れ:
- 動物性脂肪(肉の脂身、バターなど)やコレステロールを多く含む食品(卵黄、レバーなど)の過剰摂取
- トランス脂肪酸(マーガリン、ショートニングなど)の摂取
- 糖質の過剰摂取(お菓子、ジュース、炭水化物の食べ過ぎは中性脂肪の上昇につながります)
- 食物繊維の摂取不足
- 運動不足: 運動不足は、エネルギー消費を減らし、中性脂肪の増加や善玉コレステロールの減少につながります。
- 肥満: 特に内臓脂肪型の肥満は、脂質異常症と密接に関連しています。
- 喫煙: 喫煙は善玉コレステロールを減らし、悪玉コレステロールを酸化させやすくするため、動脈硬化を促進します。
- 過度な飲酒: アルコールの過剰摂取は中性脂肪を増やします。
- 遺伝的要因: 家族性高コレステロール血症など、遺伝的に脂質異常を起こしやすい体質の方もいます。
- 他の病気や薬剤の影響: 甲状腺機能低下症、腎臓病、糖尿病などの病気や、一部の薬剤(ステロイドなど)が原因となることもあります。高脂血症の原因は一つではなく、複数の要因が絡み合っていることが多いです。主な原因としては、以下のものが挙げられます。
-
加齢、閉経(女性の場合): 加齢に伴い、また女性の場合は閉経後にコレステロール値が上昇しやすくなる傾向があります。
- 食生活の乱れ:
V.高脂血症の検査方法
高脂血症の診断は、主に血液検査によって行われます。通常、空腹時に採血し、以下の項目を測定します。
- LDLコレステロール(悪玉コレステロール): 血管壁にたまり、動脈硬化を進行させる原因となります。
- 基準値: 140mg/dL未満(他のリスク因子により目標値は異なります)
- HDLコレステロール(善玉コレステロール): 血管壁にたまった余分なコレステロールを回収し、動脈硬化を防ぐ働きがあります。
- 基準値: 40mg/dL以上
- トリグリセライド(中性脂肪): 体のエネルギー源となりますが、過剰になると動脈硬化や急性膵炎のリスクを高めます。
- 基準値: 150mg/dL未満(空腹時)
- Non-HDLコレステロール: 総コレステロールからHDLコレステロールを引いた値で、動脈硬化を引き起こすすべての悪玉のコレステロールを表します。LDLコレステロールとともに管理目標として重視されています。
- 基準値: 170mg/dL未満(他のリスク因子により目標値は異なります)
これらの数値を総合的に評価し、他の危険因子(高血圧、糖尿病、喫煙歴、家族歴など)も考慮して診断および治療方針が決定されます。
VI.高脂血症の治療法
高脂血症の治療の基本は、生活習慣の改善です。それでも効果が不十分な場合や、リスクが高い場合には薬物療法が行われます。
- 生活習慣の改善
- 食事療法:
- コレステロールや飽和脂肪酸の多い食品を控える(脂身の多い肉、バター、生クリーム、洋菓子など)。
- トランス脂肪酸を多く含む食品を控える(マーガリン、ショートニング、スナック菓子など)。
- 食物繊維(野菜、海藻、きのこ、豆類、全粒穀物など)を積極的に摂取する。
- 魚(特に青魚:サバ、イワシ、アジなどEPA・DHAを多く含むもの)を積極的に摂取する。
- 糖質の摂りすぎに注意する(特に中性脂肪が高い方)。
- アルコールを控える。
- 運動療法:
- 有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリングなど)を中心に、1回30分以上、週に3回以上を目安に行う。
- 日常生活の中で、こまめに体を動かすことも大切です。
- 禁煙: 禁煙は必須です。
- 適正体重の維持: 肥満の場合は減量を目指します。
- 食事療法:
- 薬物療法 生活習慣の改善を行っても脂質の値が目標値まで下がらない場合や、心筋梗塞などのリスクが非常に高い場合には、お薬による治療が行われます。 主に使われるお薬には以下のような種類があります。
- スタチン系薬剤: 主にLDLコレステロールを下げる効果があります。
- フィブラート系薬剤: 主に中性脂肪を下げ、HDLコレステロールを上げる効果があります。
- 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬: 小腸でのコレステロール吸収を抑え、LDLコレステロールを下げます。
- 陰イオン交換樹脂(レジン): コレステロールから作られる胆汁酸の再吸収を抑え、LDLコレステロールを下げます。
- EPA・DHA製剤: 中性脂肪を下げ、動脈硬化の進行を抑える効果が期待されます。
- PCSK9阻害薬(注射薬): LDLコレステロールを強力に下げる効果があります。家族性高コレステロール血症や、スタチンで効果不十分な高リスクの患者さんに用いられます。
どのお薬を選択するかは、患者さんの脂質異常のタイプ、他の病気の有無、副作用のリスクなどを総合的に判断して決定されます。医師の指示通りにきちんと服用を続けることが大切です。
VII.当院の対応可否
当院では、高脂血症(脂質異常症)の診断から治療(生活習慣指導、薬物療法)まで一貫して対応可能です。
- 血液検査: 空腹時採血による詳細な脂質検査を実施します。
- 診断とリスク評価: 検査結果と患者様の生活習慣、既往歴、家族歴などを総合的に評価し、適切な診断と今後の治療方針をご提案します。
- 生活習慣指導: 管理栄養士や専門知識を持つスタッフが、患者様一人ひとりのライフスタイルに合わせた具体的な食事療法や運動療法について丁寧にアドバイスいたします。
- 薬物療法: 必要な場合には、最新のガイドラインに基づき、患者様に最適なお薬を選択し、処方いたします。定期的な効果判定と副作用のチェックも行い、安心して治療を継続できるようサポートいたします。
- 動脈硬化の検査: 必要に応じて、頸動脈エコー検査やABI検査(足関節上腕血圧比)などを行い、動脈硬化の進行度を評価することも可能です。
健康診断で脂質の異常を指摘された方、ご自身のコレステロールや中性脂肪についてご心配な方は、お気軽にご相談ください。
Ⅸ. Q&A
患者様からよくいただくご質問とその回答を下記にまとめております。
Q1. 高脂血症は遺伝しますか?
A1. はい、遺伝的な要因が関与することがあります。特に「家族性高コレステロール血症」という病気は、遺伝的にLDLコレステロール値が著しく高くなるもので、若いうちから動脈硬化が進行しやすいことが知られています。ご家族に高脂血症の方や若くして心筋梗塞などを起こされた方がいる場合は、一度検査を受けることをお勧めします。 ただし、遺伝的要因がなくても、生活習慣の乱れによって誰でも高脂血症になる可能性があります。
Q2. 薬を飲み始めたら、一生飲み続けないといけないのですか?
A2. 必ずしも一生飲み続けなければならないわけではありません。お薬の種類や患者さんの状態、生活習慣の改善度合いによって異なります。 生活習慣の改善(食事療法、運動療法、禁煙、減量など)をしっかり行い、脂質値が目標値まで改善し、それが維持できるようになれば、医師の判断でお薬を減らしたり、中止したりできる場合もあります。 しかし、自己判断でお薬をやめてしまうと、再び脂質値が悪化し、動脈硬化が進行するリスクが高まりますので、必ず医師にご相談ください。特に、遺伝的な要因が強い場合や、心筋梗塞などの既往がある方は、長期的な服薬が必要となることが多いです。
Q3. 食事だけで改善できますか?
A3. 軽度の高脂血症であれば、食事療法を中心とした生活習慣の改善だけで脂質値が目標値まで改善することもあります。特に中性脂肪は食事の影響を受けやすいため、糖質やアルコールの制限、青魚の摂取などで比較的効果が出やすいと言われています。 しかし、LDLコレステロールが高い場合や、遺伝的な要因が関与している場合、あるいはすでに動脈硬化が進行しているリスクが高い場合には、食事療法だけでは不十分で、薬物療法が必要となることが多いです。まずは医師に相談し、適切なアドバイスを受けることが大切です。
Q4. コレステロールが高いと言われましたが、全く症状がありません。治療は必要ですか?
A4. はい、症状がなくても治療が必要な場合があります。高脂血症は自覚症状がないまま進行し、気づいた時には心筋梗塞や脳梗塞といった重篤な病気を引き起こすことがあるため、「サイレントキラー」と呼ばれています。 健康診断などで脂質の異常を指摘された場合は、症状がなくても放置せず、一度専門医にご相談ください。医師は、脂質の数値だけでなく、年齢、性別、血圧、血糖値、喫煙習慣、家族歴など、様々なリスク因子を総合的に評価し、治療の必要性を判断します。早期に適切な対応をすることで、将来の大きな病気を予防することにつながります。
Q5. 高脂血症の予防や改善のために、具体的にどのような食事を心がければよいですか?
A5. バランスの取れた食事が基本ですが、特に以下の点を意識すると良いでしょう。
* コレステロールや飽和脂肪酸を多く含む食品を控える: 肉の脂身、レバー、卵黄(1日1個程度なら問題ないことが多いですが、医師に確認しましょう)、バター、生クリーム、インスタントラーメンなどを控えめに。
* トランス脂肪酸を避ける: マーガリン、ショートニング、それらを使用したパンや洋菓子、スナック菓子などを控えめに。
* 食物繊維をたっぷり摂る: 野菜、きのこ類、海藻類、豆類、こんにゃく、玄米や全粒粉パンなどを積極的に。
* 青魚を積極的に食べる: サバ、イワシ、サンマ、アジなどの青魚には、EPAやDHAといった良質な脂質が含まれており、中性脂肪を下げ、血栓をできにくくする効果が期待できます。
* 大豆製品を摂る: 豆腐、納豆、味噌などの大豆製品には、コレステロールを下げる効果があると言われています。
* 糖質の摂りすぎに注意: 甘いお菓子やジュース、果物の摂りすぎ、ご飯やパンなどの炭水化物の過剰摂取は中性脂肪を上げる原因になります。 * 薄味を心がける: 塩分の摂りすぎは高血圧につながり、動脈硬化のリスクを高めます。
* アルコールは適量を守る: 飲みすぎは中性脂肪を上昇させます。
【おわりに】
これらの食事療法は、高脂血症だけでなく、高血圧や糖尿病などの生活習慣病の予防・改善にもつながります。ご自身に合った食事内容については、医師や看護師にご相談ください。この記事が、高脂血症(脂質異常症)についての理解を深め、ご自身の健康管理にお役立ていただければ幸いです。気になることがあれば、どうぞお気軽に当院までご相談ください。