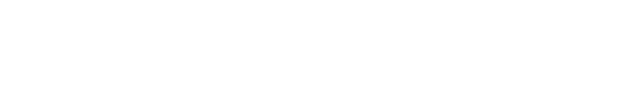高血圧
I.高血圧とは
高血圧とは、安静時の血圧が慢性的に正常値よりも高い状態を指します。血液は心臓というポンプから送り出され、血管を通って全身に届けられます。このとき、血液が血管の壁を押す力が「血圧」です。血圧には、心臓が収縮して血液を送り出すときの「収縮期血圧(最高血圧、上の血圧)」と、心臓が拡張して血液を溜め込んでいるときの「拡張期血圧(最低血圧、下の血圧)」があります。高血圧が続くと、血管の壁に常に大きな圧力がかかるため、血管が傷つきやすくなり、動脈硬化を進行させます。その結果、脳卒中(脳梗塞、脳出血)、心筋梗塞、狭心症、心不全、腎不全、大動脈瘤、眼底出血といった命に関わる重大な病気(合併症)を引き起こすリスクが高まります。
II.高血圧の診断基準
高血圧の診断は、医療機関で測定する「診察室血圧」と、ご家庭で測定する「家庭血圧」の両方を参考にします。日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン」では、以下のように定められています。
|
血圧分類 |
診察室血圧 (mmHg) |
家庭血圧 (mmHg) |
|
正常血圧 |
120未満 かつ 80未満 |
115未満 かつ 75未満 |
|
正常高値血圧 |
120~129 かつ 80未満 |
115~124 かつ 75未満 |
|
高値血圧 |
130~139 かつ/または 80~89 |
125~134 かつ/または 75~84 |
|
I度高血圧 |
140~159 かつ/または 90~99 |
135~144 かつ/または 85~89 |
|
II度高血圧 |
160~179 かつ/または 100~109 |
145~159 かつ/または 90~99 |
|
III度高血圧 |
180以上 かつ/または 110以上 |
160以上 かつ/または 100以上 |
|
(孤立性)収縮期高血圧 |
140以上 かつ 90未満 |
135以上 かつ 85未満 |
高血圧と診断されるのは、診察室血圧が140/90mmHg以上、または家庭血圧が135/85mmHg以上の場合です。
正常高値血圧や高値血圧の方も、将来的に高血圧に移行するリスクが高いため、生活習慣の見直しなど早期からの対策が推奨されます。また、診察室では血圧が高いものの家庭血圧は正常な「白衣高血圧」や、逆に診察室では正常でも家庭血圧が高い「仮面高血圧」といった状態もあります。特に仮面高血圧は合併症のリスクが高いことが知られており、家庭血圧の測定が重要となります。
III.高血圧の初期症状
前述の通り、高血圧には初期症状がほとんどありません。 多くの場合、健康診断や他の病気で医療機関を受診した際に偶然発見されます。ただし、血圧が非常に高い場合や、急激に上昇した場合などには、以下のような症状が現れることがあります。
- 頭痛、頭重感
- めまい、ふらつき
- 肩こり
- 動悸、息切れ
- 耳鳴り
- 顔のほてり
- 鼻血
これらの症状は高血圧に特有のものではなく、他の原因でも起こり得るため、自己判断せずに医療機関を受診することが大切です。症状がないからといって安心せず、定期的な血圧測定と健康診断を心がけましょう。
IV.高血圧の予後
高血圧を治療せずに放置すると、全身の血管に負担がかかり続け、動脈硬化が進行します。その結果、以下のような生命を脅かす、あるいは生活の質を著しく低下させる合併症を引き起こすリスクが高まります。
- 脳血管障害: 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血
- 心疾患: 狭心症、心筋梗塞、心不全、心肥大
- 腎疾患: 腎硬化症、慢性腎臓病(CKD)、腎不全(進行すると透析が必要になることも)
- 血管疾患: 大動脈瘤、大動脈解離、閉塞性動脈硬化症
- 眼疾患: 高血圧性網膜症、眼底出血(視力低下や失明の原因となることも)
しかし、早期に発見し、生活習慣の改善や適切な薬物療法によって血圧を良好にコントロールすることで、これらの合併症のリスクを大幅に減らすことができます。 適切な治療と管理を継続すれば、健康な方と変わらない生活を送ることも十分に可能です。
V.どういう人がなるか(原因とリスク因子)
高血圧は、主に以下の二つに分類されます。
- 本態性高血圧 (全体の約90%): 特定の病気が原因ではなく、遺伝的素因(体質)と様々な生活習慣・環境因子が複合的に関与して発症すると考えられています。主なリスク因子は以下の通りです。
- 食塩の過剰摂取: 日本人の食生活は塩分が多い傾向にあり、最大の原因の一つとされています。
- 肥満: 特に内臓脂肪型肥満は血圧を上昇させやすいです。
- 運動不足: 運動不足は肥満を助長し、血圧コントロールにも悪影響を与えます。
- 喫煙: ニコチンが血管を収縮させ、血圧を上昇させます。
- 過度の飲酒: 長期的な多量飲酒は血圧を上昇させます。
- ストレス: 精神的なストレスは交感神経を刺激し、血圧を上昇させます。
- 加齢: 年齢とともに血管の弾力性が失われ、血圧が上がりやすくなります。
- 遺伝的素因: 家族に高血圧の方がいる場合は、体質的に高血圧になりやすい傾向があります。
- 二次性高血圧 (全体の約10%) :腎臓病(腎実質性高血圧、腎血管性高血圧)、内分泌疾患(原発性アルドステロン症、クッシング症候群、褐色細胞腫、甲状腺機能亢進症など)、睡眠時無呼吸症候群、薬剤の副作用(一部の痛み止め、甘草含有製剤など)といった、特定の病気や原因が明確な高血圧です。 二次性高血圧の場合は、原因となっている病気の治療を行うことで、血圧の改善が期待できます。若年者の高血圧や、急に血圧が高くなった場合、薬が効きにくい場合などは、二次性高血圧の可能性も考慮して検査を行います。
VI.検査方法
高血圧の診断や原因検索、合併症の評価のためには、以下のような検査が行われます。
- 問診・診察:
- 自覚症状の有無と内容
- 既往歴(糖尿病、脂質異常症、腎臓病など)
- 家族歴(高血圧、心血管疾患、脳血管疾患など)
- 生活習慣(食事内容、運動習慣、喫煙、飲酒、睡眠、ストレスなど)
- 服用中の薬(市販薬、サプリメント含む)
- 血圧測定(複数回測定、左右差の確認など)
- 聴診(心音、血管雑音など)
- 家庭血圧測定の指導: 正しい血圧測定方法を指導し、朝晩の家庭血圧を記録していただきます。診察室血圧だけでは分からない血圧の変動(白衣高血圧、仮面高血圧など)を把握するために非常に重要です。
- 血液検査:
- 腎機能(BUN、クレアチニン、eGFR)
- 電解質(ナトリウム、カリウムなど)
- 脂質(総コレステロール、LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
- 血糖値、HbA1c(糖尿病の指標)
- 尿酸値
- 貧血の有無
- 二次性高血圧が疑われる場合は、各種ホルモン検査(レニン、アルドステロン、カテコールアミンなど)
- 尿検査:
- 尿蛋白、尿糖、尿潜血など(腎臓への影響を評価)
- 心電図検査 (ECG/EKG):
- 心肥大(高血圧による心臓への負担)、不整脈、狭心症や心筋梗塞の兆候がないかなどを調べます。
- 胸部X線検査:
- 心臓の大きさ(心拡大)や形、肺の状態(うっ血の有無など)を確認します。
- 眼底検査:
- 眼の奥の網膜血管を観察し、高血圧による動脈硬化の程度や出血の有無などを評価します。
- その他(必要に応じて):
- 心エコー検査(心臓超音波検査): 心臓の動きや大きさ、壁の厚さ、弁の状態などを詳しく調べます。
- 腹部エコー検査、CT、MRI: 二次性高血圧の原因となる腎臓や副腎の異常を調べる場合に行います。
- 睡眠時無呼吸症候群の検査 (PSG): 睡眠中の呼吸状態を評価します。
これらの検査を組み合わせて、高血圧の程度、原因、合併症の有無を総合的に評価し、治療方針を決定します。
VII.治療方法
高血圧治療の目標は、血圧を適切なレベルにコントロールし、心血管疾患や腎臓病などの合併症を予防し、健康寿命を延ばすことです。治療の基本は、生活習慣の修正と薬物療法です。
- 生活習慣の是正 (非薬物療法): すべての高血圧患者さんにとって基本となる治療です。これだけで血圧が十分に下がることもありますし、薬物療法の効果を高めるためにも重要です。
- 減塩: 1日の食塩摂取量を6g未満にすることが目標です。薄味に慣れ、だしや香辛料を上手に使いましょう。加工食品や外食の塩分量にも注意が必要です。
- 食事療法(DASH食など): 野菜、果物、低脂肪乳製品を積極的に摂り、飽和脂肪酸やコレステロールの摂取を控える食事(DASH食:Dietary Approaches to Stop Hypertension)も推奨されています。
- 適正体重の維持(減量): 肥満の方は、体重を減らすことで血圧が下がることが期待できます。
- 運動療法: ウォーキング、ジョギング、水泳などの有酸素運動を、1回30分以上、できれば毎日(少なくとも週3回以上)行うことが推奨されます。医師に相談の上、無理のない範囲で始めましょう。
- 節酒: アルコールの過剰摂取は血圧を上昇させます。男性なら1日エタノール換算で20~30mL以下(日本酒1合、ビール中瓶1本、焼酎半合、ワイン2杯程度)、女性はその半分程度が目安です。
- 禁煙: 喫煙は血圧を上げるだけでなく、動脈硬化を著しく進行させます。禁煙は必須です。禁煙外来なども活用しましょう。
- 十分な睡眠と休養、ストレス管理: 質の良い睡眠をとり、ストレスを上手に発散することも大切です。
- 薬物療法 (降圧薬治療): 生活習慣の修正を行っても血圧が目標値まで下がらない場合や、すでに合併症がある場合、高リスクの場合などには、降圧薬による治療を開始します。
- 降圧目標: 年齢や合併症の有無によって異なりますが、一般的には診察室血圧130/80mmHg未満(家庭血圧125/75mmHg未満)を目指します。75歳以上の高齢者では、より緩やかな目標(例:140/90mmHg未満)となることもあります。医師と相談して個別の目標を設定します。
- 降圧薬の種類:
- カルシウム拮抗薬: 血管を拡げて血圧を下げます。
- ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)/ACE阻害薬(アンジオテンシン変換酵素阻害薬): 血管を収縮させる物質の作用を抑えて血圧を下げ、臓器保護作用も期待されます。
- 利尿薬: 体内の余分な塩分と水分を尿として排泄し、血液量を減らして血圧を下げます。
- β遮断薬: 心臓の働きを少し抑えて心拍数を減らし、血圧を下げます。
- その他、α遮断薬などもあります。
- 薬剤の選択: 患者さんの年齢、合併症(糖尿病、腎臓病、心不全など)、副作用などを考慮して、最適な薬剤が選択されます。最初は1種類の薬から始めることが多いですが、効果が不十分な場合は、作用の異なる複数の薬を組み合わせて使用することもあります(併用療法)。
- 自己判断での中断は禁物: 降圧薬は、血圧をコントロールするために継続して服用することが基本です。症状がないからといって自己判断で中断したり、量を減らしたりすると、血圧が再上昇し、合併症のリスクが高まる可能性があります。必ず医師の指示に従ってください。
Ⅷ.当院の対応可否
当院では、高血圧が疑われる患者様、またはその予防・管理をご希望の患者様に対して、以下の総合的な対応が可能です。
- 専門的な問診と診察: 血圧の状況、生活習慣、家族歴などを詳しく伺い、総合的な診察を行っています。
- 各種検査の実施: 血液検査、尿検査、心電図検査などを実施し、高血圧の診断、原因検索、合併症の評価を行います。家庭血圧測定の指導も積極的に行います。
- 診断と治療方針の決定: 検査結果と患者様の状態を総合的に判断し、個別の治療目標と治療計画を立案します。
- 生活習慣指導: 減塩指導、食事療法、運動療法、禁煙指導など、患者様一人ひとりに合わせた具体的なアドバイスを行います。管理栄養士による栄養指導も可能です(連携施設への紹介となる場合があります)。
- 薬物療法による管理: 必要な場合には、エビデンスに基づいた適切な降圧薬を選択し、定期的な効果判定と副作用チェックを行いながら、きめ細やかな薬物療法を提供します。
- 二次性高血圧のスクリーニングと専門医療機関へのご紹介: 二次性高血圧が疑われる場合には、必要な初期検査を行い、より専門的な検査や治療が必要と判断された場合には、適切なタイミングで責任をもって連携先の高度医療機関へご紹介いたします。
- 定期的なフォローアップと合併症予防: 長期的な視点で血圧管理をサポートし、合併症の早期発見・予防に努めます。
高血圧は、早期からの適切な管理が非常に重要です。「健康診断で血圧が高いと言われた」「最近、血圧が気になる」「家族に高血圧の人がいる」など、ご不安やお悩みをお持ちの方は、どうぞお気軽に当院にご相談ください。医師、看護師、スタッフ一同、皆様の健康をサポートさせていただきます。
Ⅸ.Q&A
ここでは、高血圧に関して患者様からよくいただくご質問や、特に知っておいていただきたいポイントについて、Q&A形式でお答えします。
Q1. 家庭血圧はなぜ測る必要があるのですか?正しい測り方は?
A1. 家庭血圧は、診察室での血圧測定だけではわからない普段の血圧の状態を知るために非常に重要です。診察室では緊張して血圧が上がってしまう「白衣高血圧」や、逆に診察室では正常でも家庭では高い「仮面高血圧」を見つけることができます。特に仮面高血圧は心血管疾患のリスクが高いとされており、早期発見・治療が大切です。
【正しい家庭血圧の測り方】
- 測定時間: 朝(起床後1時間以内で、排尿後、朝食・服薬前)と夜(就寝前)の2回測定が基本です。
- 測定環境: 静かで適温の部屋で、椅子に座って1~2分安静にしてから測定します。
- 測定姿勢: 背もたれのある椅子に足を組まずに座り、腕は心臓の高さで測定します。カフ(腕帯)は、きつすぎず緩すぎず、指1本が入る程度に巻きます。
- 記録: 測定した血圧値と脈拍数、測定日時を記録しましょう。市販の血圧手帳やアプリを利用すると便利です。
- 機器: 上腕式(腕にカフを巻くタイプ)の自動血圧計が推奨されます。
Q2. 減塩はどのくらいすれば良いですか?具体的なコツは?
A2. 日本高血圧学会では、高血圧患者さんの1日の食塩摂取目標量を6g未満としています。日本人の平均食塩摂取量は約10gと言われており、意識的な減塩が必要です。
【減塩の具体的なコツ】
- 調味料を減らす: 醤油やソースは「かける」より「つける」、味噌汁は具だくさんにして汁の量を減らすなど工夫しましょう。
- だしや香辛料を活用する: 昆布やかつお節でしっかりだしを取り、ハーブやスパイス、香味野菜(生姜、ニンニク、ネギなど)で風味豊かにすると、薄味でも美味しく食べられます。
- 加工食品や外食に注意: ハム、ソーセージ、練り製品、漬物、インスタント食品、スナック菓子などは塩分が多い傾向があります。成分表示を確認する習慣をつけましょう。外食では、麺類の汁を残す、定食の小鉢は味の薄いものを選ぶなどの工夫が大事です。
- 「減塩」「無塩」表示の食品を選ぶ: 調味料や食品を選ぶ際に参考にしましょう。
- 新鮮な食材の味を活かす: 素材そのものの味を活かした調理を心がけましょう。
- ゆっくりよく噛んで食べる: 満腹感が得られやすくなり、薄味でも満足しやすくなります。
いきなり厳しい減塩は難しいかもしれませんが、少しずつでも続けることが大切です。
Q3. 高血圧の薬は一度飲み始めたら、一生やめられないのですか?
A3. 必ずしも一生やめられないわけではありません。 生活習慣の改善(減塩、減量、運動など)をしっかり行い、血圧が長期間安定してコントロールできるようになった場合には、医師の判断で薬の量を減らしたり、中止したりできることもあります。 しかし、多くの場合、本態性高血圧は体質的な要因も関わっているため、薬を中止すると再び血圧が上昇することが少なくありません。自己判断で薬をやめてしまうと、血圧が急上昇して危険な状態になることもありますので、必ず医師に相談してください。 薬を飲み続けることのメリット(合併症予防)とデメリット(副作用のリスクなど)をよく理解し、医師と相談しながら治療を進めていくことが大切です。
Q4. 降圧薬に副作用はありますか?
A4. どんな薬にも副作用の可能性はありますが、降圧薬は比較的安全性が高く、重篤な副作用は稀です。 主な副作用としては、カルシウム拮抗薬では顔のほてり、頭痛、動悸、歯肉増殖、足のむくみなど、ARB/ACE阻害薬では空咳(ACE阻害薬)、めまい、高カリウム血症など、利尿薬では電解質異常(低カリウム血症など)、脱水、頻尿など、β遮断薬では徐脈、倦怠感などがあります。 副作用の出方や程度には個人差があります。気になる症状が現れた場合は、自己判断で薬をやめずに、必ず医師や薬剤師にご相談ください。多くの場合は、薬の種類を変更したり、量を調整したりすることで対応できます。
Q5. 若くても高血圧になりますか?原因は何ですか?
A5. はい、若い方でも高血圧になることがあります。 若い方の高血圧の原因としては、
- 生活習慣の乱れ: 濃い味付けの食事、外食やインスタント食品の多用、運動不足、肥満、喫煙、過度の飲酒、ストレスなどが挙げられます。
- 二次性高血圧: 腎臓病、甲状腺機能亢進症、原発性アルドステロン症などの内分泌疾患、睡眠時無呼吸症候群など、特定の病気が原因となっている場合もあります。若年者の高血圧では、二次性高血圧の割合が比較的高いため、原因を調べることが重要です。 健康診断などで血圧が高いと指摘された場合は、放置せずに医療機関を受診しましょう。
Q6. 症状がないのに、なぜ治療が必要なのですか?
A6. 高血圧は自覚症状がほとんどないため、「サイレントキラー(静かなる殺人者)」と呼ばれています。症状がなくても、高い血圧が続くことで血管に常に負担がかかり、動脈硬化が進行します。その結果、将来的に脳卒中、心筋梗塞、心不全、腎不全といった命に関わる重大な合併症を引き起こすリスクが高まります。 高血圧の治療は、これらの怖い合併症を予防し、健康寿命を延ばすために行います。症状がないからといって放置せず、医師の指示に従って適切な治療を続けることが非常に大切です。
Q7. 運動はどのくらいすれば良いですか?どんな運動が良いですか?
A7. 高血圧の改善・予防には、ウォーキング、軽いジョギング、サイクリング、水泳などの有酸素運動が推奨されます。 目標としては、1回30分以上を週に3回以上、できれば毎日行うのが理想です。まとめて時間が取れない場合は、10分程度の運動を数回に分けても効果があります。 運動の強度は、「ややきつい」と感じる程度が良いでしょう。息が弾むものの、会話ができるくらいが目安です。 ただし、重症の高血圧の方や心臓に合併症がある方は、運動によってかえって状態が悪化する可能性もあるため、必ず事前に医師に相談し、適切な運動の種類や強度について指示を受けてください。 準備運動と整理運動も忘れずに行い、無理のない範囲で継続することが大切です。
Q8. ストレスも高血圧の原因になりますか?
A8. はい、ストレスは高血圧の大きな要因の一つです。 精神的なストレスを感じると、交感神経が活発になり、血管が収縮したり、心拍数が増加したりして血圧が上昇します。また、ストレスが続くと、暴飲暴食や喫煙、飲酒量の増加など、生活習慣の乱れにもつながりやすく、間接的にも高血圧を悪化させる可能性があります。 ストレスを完全に避けることは難しいかもしれませんが、自分なりのリラックス方法を見つける(趣味、音楽鑑賞、入浴、軽い運動など)、十分な睡眠と休息をとる、悩みを一人で抱え込まずに相談するなど、ストレスと上手に付き合っていくことが大切です。
Q9. 「白衣高血圧」や「仮面高血圧」とは何ですか?
A9.
- 白衣高血圧: 普段の家庭血圧は正常範囲なのに、医療機関で医師や看護師(白衣)の前で測定すると血圧が高くなってしまう状態です。緊張やストレスが原因と考えられています。通常、すぐに治療の対象とはなりませんが、将来的に持続性高血圧に移行するリスクがあるため、定期的な経過観察と家庭血圧測定が重要です。
- 仮面高血圧: 診察室での血圧は正常範囲なのに、家庭血圧や24時間自由行動下血圧測定(ABPM)では高い値を示す状態です。早朝高血圧や夜間高血圧などがこれにあたります。通常の高血圧と同様に心血管疾患のリスクが高いとされており、見逃されやすいため注意が必要です。家庭血圧測定が診断に非常に役立ちます。
Q10. 血圧を下げる効果が期待できる食べ物や飲み物はありますか?
A10. 特定の食品だけを摂れば血圧が劇的に下がるというものはありませんが、バランスの取れた食事の中で、血圧コントロールに良いとされる栄養素を積極的に摂ることは有効です。
- カリウムを多く含む食品: カリウムは体内の余分なナトリウム(塩分)の排泄を促す働きがあります。野菜(ほうれん草、かぼちゃ、アボカドなど)、果物(バナナ、キウイ、りんごなど)、いも類、海藻類、豆類に多く含まれます。ただし、腎機能が低下している方はカリウムの摂取制限が必要な場合があるので、医師に相談してください。
- カルシウムを多く含む食品: 牛乳・乳製品、小魚、大豆製品、緑黄色野菜など。
- マグネシウムを多く含む食品: 海藻類、豆類、ナッツ類、緑黄色野菜など。
- 食物繊維を多く含む食品: 野菜、果物、きのこ類、海藻類、豆類、全粒穀物など。コレステロールの吸収を抑えたり、血糖値の急上昇を防いだりする効果も期待できます。
- EPA・DHAを多く含む青魚: さば、いわし、さんまなどの青魚に含まれるEPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)は、血液をサラサラにし、動脈硬化の進行を抑える効果が期待されます。
- お茶: 緑茶に含まれるカテキンや、一部の健康茶に含まれる成分には、血圧上昇を緩やかにする可能性が報告されていますが、あくまで補助的なものと考えましょう。
これらの食品をバランス良く取り入れ、何よりも減塩を中心とした食生活全体を見直すことが重要です。
このQ&Aで皆様の高血圧に対する理解を深め、適切な対応をとるための一助となれば幸いです。ご不明な点やご心配なことがございましたら、どうぞお気軽に当院にご相談ください。