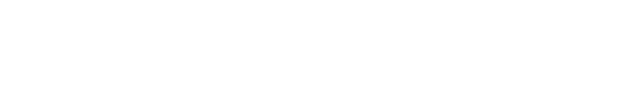逆流性食道炎
I.逆流性食道炎とは
逆流性食道炎は、胃酸などが食道に逆流して炎症を起こす病気です。
食道には、胃酸が逆流しないように、胃と食道のつなぎ目にある「下部食道括約筋」という筋肉で入口が締まっています。一般的に、健康な人でも、食べ物が食道を通るときには、一時的な胃酸の逆流が起こります。 しかし、食べ物が通るとき以外でも下部食道括約筋が緩むと、胃から食道への逆流が発生します。食道は、胃と違って強い酸性の胃液から粘膜を守ることができないため、胃酸の逆流により、食道粘膜にびらんや潰瘍が生じます。
逆流性食道炎は、中高年から高齢者に多く見られますが、適切な治療を受けることで改善することができます。
出典:国立長寿医療研究センター 逆流性食道炎ってどんな病気?
II.逆流性食道炎の初期症状
逆流性食道炎の主な初期症状は以下の通りです。
- 胸やけがする、胃がむかむかする
- 胃もたれする
- みぞおちが痛む
- 酸っぱいものがこみ上げてくる
- お腹が張る
などの症状がある場合は、逆流性食道炎の可能性があります。
III.逆流性食道炎の予後
逆流性食道炎は、治療開始から1~2週間で改善することが多いです。しかし、一時的に症状が改善した場合でも、再発する可能性が高いため長期的に治療を継続しましょう。
また、逆流性食道炎の治療を適切に行わなかった場合は、食道がんの発症につながる可能性があります。
症状が出た場合には、早めに治療を開始して炎症を治すことが大切です。
IV. 逆流性食道炎になる原因
逆流性食道炎の主な原因は以下の通りです。
- 加齢による下部食道括約筋の低下
- 生活習慣の乱れ
- 肥満
など
特に、逆流性食道炎になりやすい方は、食習慣の乱れが原因のことが多いです。
下記に当てはまる方は、注意しましょう。
- 1度にたくさんの量を食べ過ぎる
- 早食いの習慣がある
- 高脂肪の食事をとることが多い
- 飲酒や喫煙の習慣がある
- 寝る直前に食べる
など
V.逆流性食道炎の検査方法
逆流性食道炎の主な検査方法は、以下の通りです。
・食道内視鏡検査
口や鼻から内視鏡(細くて長い管)を食道まで入れて、食道の粘膜状態を確認します。逆流性食道炎だけでなく、がんや他の病気の有無を確認することができます。
・食道内pHモニタリング検査
逆流性食道炎の程度を診断します。直径2㎜程度のチューブを鼻から入れて、食道内の酸度(pH)を24時間測定します。胃酸が逆流するとpH値の低下するため、pH4以下の時間が1日4~5%以上になっていないかを確認します。
・食道内圧測定検査
内圧測定の装置を鼻から食道に入れて、下部食道括約筋の内圧を測定し、食道の動きを確認します。下部食道括約筋の内圧や食道の動きを確認することで、逆流の程度がわかります。
VI. 逆流性食道炎の治療法
逆流性食道炎の主な治療法は、「生活習慣の改善」と「薬物療法」です。
生活習慣の改善や、薬物療法をしても症状が回復しない場合、外科治療(手術)も検討されます。
<生活習慣の改善>
- 暴飲暴食をしない
- 脂肪分やたんぱく質の過剰摂取を控える
- 食後2~3時間空けて就寝する
- 胃酸を増加させる食品(香辛料や甘い物、かんきつ類、カフェインなど)を控える
- 禁煙する
- アルコールの量を控える
- 肥満を解消するために軽い運動を習慣化する
- 締め付けの強い洋服は避ける
- 正しい姿勢を心がける
など、まずはストレスのない範囲で生活習慣を改善しましょう。
<薬物療法>
胃酸分泌抑制薬の服用が中心となります。主に処方される薬は以下の種類です。
- プロトンポンプ阻害薬(PPI)
- H2ブロッカー
- 消化管運動機能改善剤
- 制酸薬
- 粘膜保護薬
など、症状に合わせた薬物療法を行います。
<外科治療(手術)>
薬物療法をしても症状が改善されない、体質の関係で服薬ができないなどの場合は、外科治療(手術)を視野に入れます。
外科治療(手術)は、主に腹腔鏡を使って行います。腹腔鏡による手術は、腹部に5~12mm程度の穴を5カ所開けるため、約1週間の入院が必要です。