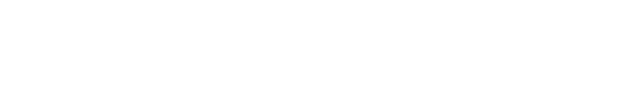貧血
その動悸や息切れ、もしかしたら「貧血」が原因かもしれません
「最近、階段を上るだけで息が切れる」「朝、すっきりと起きられない」「めまいや立ちくらみが頻繁にある」。このような症状に心当たりはありませんか?心臓が専門の循環器内科クリニックには、動悸や息切れといった症状で受診される患者様が数多くいらっしゃいます。もちろん心臓の病気が隠れていることもありますが、実は「貧血」が原因であることも少なくありません。
今回は、皆さまの健康に深く関わる「貧血」について、その全体像から当院での対応まで、詳しく解説していきます。
I. 貧血とは
貧血とは、血液中のヘモグロビン(血色色素)の濃度が低下した状態を指します。ヘモグロビンは、赤血球の中に存在し、肺で取り込んだ酸素を全身の臓器や組織に運ぶという、生命維持に不可欠な役割を担っています。
そのため、ヘモグロビンが減少すると、体は酸素不足に陥り、様々な症状を引き起こします。世界保健機関(WHO)の基準では、成人男性でヘモグロビン値が未満、成人女性(妊娠中を除く)で未満になると、貧血と診断されます。
II. 貧血の初期症状
貧血の症状は、ゆっくりと進行する場合、体が慣れてしまい自覚しにくいこともあります。しかし、以下のようなサインに気づいたら注意が必要です。これらは、心臓の病気の症状と非常によく似ています。
- 全身の症状:疲れやすい、だるい(倦怠感)、顔色が悪い(蒼白)
- 心臓・肺の症状:動悸、息切れ、胸の痛み
- 脳の症状:めまい、立ちくらみ、頭痛、集中力の低下
- その他の症状:爪がもろくなる・反り返る(スプーンネイル)、氷などを無性に食べたくなる(異食症)、耳鳴り、食欲不振
これらの症状は、体が酸素不足を補おうとして心臓や肺に負担がかかるために現れます。
III. 貧血の予後
貧血の予後(病気の経過の見通し)は、その原因や重症度、そして治療への反応によって大きく異なります。
最も多い鉄欠乏性貧血は、原因を特定し、鉄剤の服用などで適切に治療すれば、一般的に予後は良好です。数ヶ月でヘモグロビン値は改善しますが、体内の貯蔵鉄(フェリチン)が満たされるまで、医師の指示に従って治療を続けることが大切です。
しかし、貧血を放置することは大変危険です。特に、心臓に持病がある方が貧血を合併すると、心臓への負担が増大し、心不全を悪化させる可能性があります。心臓病、腎臓病、そして貧血が互いに悪影響を及ぼしあう状態は「心腎貧血症候群」とも呼ばれ、生命予後に関わるため、循環器内科医による慎重な管理が求められます。
また、再生不良性貧血など、特殊なタイプの貧血は専門的な治療が必要となる場合があります。
IV. 貧血になる原因
貧血は、大きく分けて以下の3つの原因で起こります。
-
赤血球が作られない(産生の低下)
- 鉄欠乏性貧血:最も多いタイプ。ヘモグロビンの材料である鉄分の不足が原因。偏食、過度なダイエット、成長期、妊娠・授乳など。
- ビタミンB12・葉酸欠乏性貧血:赤血球の成熟に必要なビタミンB12や葉酸の不足。
- 腎性貧血:腎臓の機能が低下し、赤血球の産生を促すホルモン(エリスロポエチン)が不足する。
- 再生不良性貧血:血液細胞を作り出す骨髄の機能が低下する病気。
-
赤血球が失われる(出血)
- 慢性の出血:胃潰瘍、十二指腸潰瘍、大腸がん、子宮筋腫、過多月経などにより、気づかないうちに少量ずつ出血が続く。
-
赤血球が壊される(溶血)
- 溶血性貧血:赤血球が通常より早く壊されてしまう状態。自己免疫の異常などが原因となることがある。
V. 貧血の検査方法
貧血が疑われる場合、まずは血液検査を行います。 この検査では、ヘモグロビン値(Hb)、赤血球数(RBC)、ヘマトクリット値(Ht)などを測定し、貧血の有無と程度を評価します。
さらに、貧血の原因を特定するために、以下の項目も調べます。
- MCV(平均赤血球容積):赤血球の大きさ。貧血の種類を推測する手がかりになります。
- 血清鉄、フェリチン:体内の鉄分の量や貯蔵鉄の状態を評価します。
これらの血液検査で鉄欠乏性貧血と診断された場合、特に男性や閉経後の女性では、消化管からの出血が隠れている可能性を考慮し、便潜血検査や胃・大腸内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)をお勧めすることがあります。女性の場合は、婦人科系の疾患が原因となることも多いため、婦人科との連携も重要になります。
VI. 貧血の治療法
貧血の治療は、その原因に対して行われます。
- 鉄欠乏性貧血:治療の基本は、不足している鉄分を補う鉄剤(内服薬)の服用です。吐き気などの胃腸症状が出ることがありますが、最近では副作用の少ない薬や、1日おきの服用でも効果が期待できることが分かってきています。改善が見られない場合や内服が困難な場合は、注射による鉄剤投与を行うこともあります。
- その他の貧血:ビタミン欠乏であればビタミンの補充、腎性貧血であればエリスロポエチン製剤の注射など、原因に応じた治療を行います。
最も重要なのは、貧血の原因となっている病気(出血の原因など)を特定し、その治療を並行して行うことです。また、日頃からバランスの取れた食事を心がけることも、貧血の予防・改善につながります。
VII. 当院の対応可否
当院は循環器内科クリニックですが、動悸や息切れといった症状の背景に貧血が隠れていることが多いため、貧血の診断・治療にも積極的に対応しております。
健康診断で貧血を指摘された方、気になる症状がある方は、お気軽にご相談ください。血液検査により貧血の有無や種類を迅速に診断し、治療を開始することが可能です。
貧血の原因精査のために消化器内科や婦人科など他の専門科での検査・治療が必要と判断した場合は、地域の信頼できる医療機関と連携し、適切な治療を受けていただけるようサポートいたします。心臓と血液は密接な関係にあります。循環器の専門家として、全身の状態を考慮した上で、皆さまの健康を支えてまいります。
Ⅷ. Q&A
患者様からよくいただくご質問にお答えします。
Q1. 動悸や息切れがします。心臓が悪いのでしょうか、それとも貧血でしょうか?
A1. 動悸や息切れは、心臓の病気と貧血のどちらでも起こりうる代表的な症状です。貧血になると、全身に十分な酸素を届けるために心臓が普段より多くの血液を送り出そうと頑張るため、動悸や息切れを感じやすくなります。自己判断は難しいため、まずは循環器内科にご相談ください。診察と簡単な検査で、原因を突き止めることが重要です。
Q2. 貧血を予防するには、どんな食事をすれば良いですか?レバーが苦手です。
A2. 鉄分には、肉や魚に含まれる「ヘム鉄」と、野菜や豆類に含まれる「非ヘム鉄」があります。ヘム鉄の方が吸収率が高いとされています。レバー以外にも、牛肉の赤身、マグロやカツオなどの赤身魚、あさりなどに多く含まれます。 非ヘム鉄は、ほうれん草、小松菜、ひじき、大豆製品などに豊富です。非ヘム鉄は、ビタミンC(果物や野菜に多い)や動物性たんぱく質と一緒にとると吸収率がアップします。バランスの良い食事を心がけることが最も大切です。
Q3. 鉄剤のサプリメントを自分で飲んでも良いですか?
A3. 貧血の症状があるからといって、自己判断でサプリメントを摂取することはお勧めできません。貧血の原因は様々であり、鉄分が不足していないタイプの貧血もあります。体内に鉄が過剰に蓄積すると、かえって肝臓などに負担をかけることもあります。まずは医療機関で血液検査を受け、医師の診断のもとで適切な治療を開始してください。
Q4. 貧血は女性だけの病気というイメージがありますが、男性もなりますか?
A4. はい、男性も貧血になります。女性は月経により定期的に出血があるため貧血になりやすいですが、男性や閉経後の女性が鉄欠乏性貧血になった場合、胃や大腸など消化管からの出血が原因となっている可能性があります。潰瘍やがんなどの重大な病気が隠れているサインかもしれないため、より注意深い検査が必要です。
気になる症状があれば、決して放置せず、お気軽に当院までご相談ください。