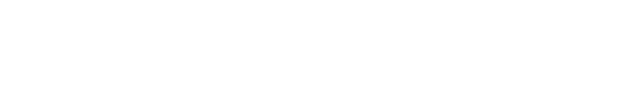肺炎
「ただの風邪だと思っていたら、実は肺炎だった」というケースは少なくありません。特に心臓に持病をお持ちの方やご高齢の方にとって、肺炎は重症化しやすく、注意が必要な病気です。
今回は、循環器内科の観点からも重要となる「肺炎」について、その症状から治療、予防までを詳しく解説します。
Ⅰ.肺炎とは
肺炎は、主に細菌やウイルスなどの病原体が肺に感染し、炎症を引き起こす病気です。肺の中には、酸素と二酸化炭素の交換を行う「肺胞(はいほう)」という小さな袋状の組織があり、肺炎になるとこの肺胞に炎症が起きて、膿や水分が溜まってしまいます。その結果、酸素の取り込みがうまくいかなくなり、咳や痰、息切れ、発熱などの症状が現れます。日本の死因順位でも常に上位にあり、特に高齢者や基礎疾患をお持ちの方にとっては命に関わることもあるため、早期発見・早期治療が非常に重要です。
Ⅱ.肺炎の初期症状
肺炎の初期症状は、風邪とよく似ています。しかし、以下のような症状が長引く場合は注意が必要です。
- 38℃以上の高熱が続く
- 激しい咳や、色のついた痰(黄色、緑色、錆び色など)が出る
- 胸の痛み
- 呼吸が速くなる、息苦しさを感じる
- 強い倦怠感、食欲不振
特にご高齢の方では、典型的な症状が出にくく、「なんとなく元気がない」「食欲がない」といった変化がサインであることもあります。周りの方が変化に気づいてあげることが大切です。
III. 肺炎の予後
適切な治療を行えば、多くの場合は回復に向かいます。しかし、発見が遅れたり、もともと心臓病や糖尿病などの基礎疾患をお持ちの方、ご高齢の方では重症化しやすく、入院治療が必要になることも少なくありません。
重症化すると、呼吸不全や敗血症(血液中に細菌が入り込み、全身に重い炎症が起きる状態)などを引き起こし、命に関わる危険性もあります。また、一度肺炎にかかると、肺の機能が完全に元に戻らない場合もあります。
Ⅳ.肺炎になる原因
肺炎の主な原因は、病原体への感染です。原因となる病原体は様々ですが、代表的なものには以下が挙げられます。
- 細菌性肺炎:肺炎球菌、インフルエンザ菌などが代表的です。日常生活で感染する「市中肺炎」の多くは、この細菌性が原因です。
- ウイルス性肺炎:インフルエンザウイルス、コロナウイルス、RSウイルスなどが原因となります。
非定型肺炎:マイコプラズマやクラミジアなど、上記の細菌とは異なる性質を持つ病原体によって引き起こされます。比較的若い世代に多く、しつこい空咳が特徴的です。- 誤嚥(ごえん)性肺炎:食べ物や唾液、胃液などが誤って気管に入り、それに含まれる細菌が原因で起こる肺炎です。嚥下(えんげ)機能が低下したご高齢の方に多く見られます。
特に心不全などの循環器疾患をお持ちの方は、体の抵抗力が落ちているため、肺炎にかかりやすくなる傾向があります。
Ⅴ.肺炎の検査方法
肺炎が疑われる場合、以下のような検査を組み合わせて診断します。
- 問診・聴診:症状や経過を詳しくお伺いし、聴診器で肺の音に異常(雑音など)がないかを確認します。
- 画像検査(胸部X線・CT):肺炎の確定診断に最も重要です。肺に炎症が起きている部分は白く写るため、炎症の場所や広がり具合を確認できます。
- 血液検査:体内の炎症の程度(CRPや白血球数)や、酸素が十分に行き渡っているか(酸素飽和度)などを調べます。
- 喀痰(かくたん)検査:痰を採取し、原因となっている病原体を特定します。原因菌に合った適切な抗菌薬を選択するために重要な検査です。
Ⅵ.肺炎の治療法
肺炎の治療の基本は、原因となっている病原体に対する薬物療法です。
- 抗菌薬(抗生物質):細菌性肺炎の場合に最も重要な治療です。原因菌を特定し、その菌に効果のある抗菌薬を点滴または内服で投与します。
- 抗ウイルス薬:インフルエンザウイルスなどが原因の場合に使用します。
- 対症療法:咳を鎮める薬、痰を出しやすくする薬、熱を下げる薬などを症状に合わせて使用します。
- 酸素投与:呼吸が苦しく、血液中の酸素が不足している場合には、酸素吸入を行います。
軽症の場合は外来での内服治療が可能ですが、重症の場合や、脱水、食事がとれないなどの状態が見られる場合は、入院して点滴治療を行う必要があります。
VII. 当院での対応
当院では、循環器内科の専門医が、心臓の状態も考慮しながら肺炎の的確な診断と治療を行います。
胸部X線検査や血液検査により、肺炎の迅速な診断が可能です。軽症から中等症の肺炎であれば、外来での治療に対応いたします。治療経過もしっかりとフォローアップし、患者様一人ひとりの状態に合わせたきめ細やかな医療を提供します。
重症で入院が必要と判断される場合や、より専門的な呼吸器内科での検査・治療が必要な場合は、責任をもって地域の基幹病院や専門医療機関へ迅速にご紹介いたします。長引く咳や発熱など、気になる症状がございましたら、お早めにご相談ください。
Ⅷ. Q&A(よくあるご質問)
Q1. 肺炎は人にうつりますか?
A1. 原因となる病原体によりますが、多くの肺炎は咳やくしゃみなどの飛沫(ひまつ)によって人から人へとうつる可能性があります。特に、マイコプラズマ肺炎やインフルエンザウイルス、新型コロナウイルスによる肺炎は感染力が強いことで知られています。ご家庭内や職場などで感染を広げないためにも、マスクの着用や手洗い、咳エチケットなどの基本的な感染対策が重要です。
Q2. 風邪と肺炎はどうやって見分ければよいですか?
A2. 風邪の多くは、鼻水やのどの痛みが主な症状で、発熱しても比較的軽度で数日で改善することが多いです。一方、肺炎は38℃以上の高熱、激しい咳、色のついた痰、息苦しさなどが特徴で、これらの症状が長引く傾向があります。風邪薬を飲んでも症状が改善しない、あるいは悪化する場合は、肺炎を疑って早めに医療機関を受診してください。
Q3. 肺炎を予防する方法はありますか?
A3. はい、予防は可能です。最も効果的な予防法の一つがワクチン接種です。特に高齢者の肺炎の原因として最も多い「肺炎球菌」に対するワクチンは、重症化を防ぐ効果が期待できます。また、インフルエンザワクチンの接種も、インフルエンザの合併症としての肺炎を防ぐために非常に重要です。その他、日頃からの手洗い・うがい、十分な休養と栄養、禁煙、持病のコントロール、口腔ケア(誤嚥性肺炎予防のため)などが有効です。
気になる症状があれば、自己判断せずに、いつでもお気軽に当院へご相談ください。