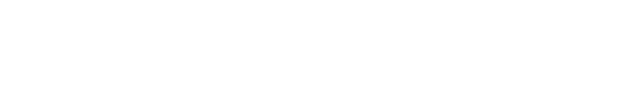睡眠時無呼吸症候群
Ⅰ. 睡眠時無呼吸症候群とは
睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome:SAS)とは、眠っている間に呼吸が止まる状態(無呼吸)や、呼吸が浅くなる状態(低呼吸)が何度も繰り返される病気です。医学的には、10秒以上の呼吸停止を無呼吸とし、1時間あたりに無呼吸や低呼吸が5回以上起こる場合に診断されます。
呼吸が止まることで体に取り込まれる酸素の量が減少し、体に負担がかかります。その結果、睡眠の質が低下し、日中の活動に支障をきたすだけでなく、様々な生活習慣病のリスクを高めることがわかっています。
大きく分けて、以下の2つのタイプがあります。
- 閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS): 喉や気道が物理的に狭くなる、または塞がってしまうことで起こります。SASの大部分がこのタイプです。
- 中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSAS): 脳の呼吸中枢からの呼吸指令が出なくなることで起こります。心不全や脳血管障害などの病気が原因となることがあります。
Ⅱ. 睡眠時無呼吸症候群の初期症状
睡眠時無呼吸症候群の症状は、睡眠中に起こるものと、日中に現れるものがあります。ご自身やご家族に以下のような症状がないか確認してみましょう。
睡眠中の主な症状:
- 大きないびき: しばしば呼吸が止まるとともに、いびきも止まり、その後あえぐような激しい呼吸とともに再びいびきをかき始めます。
- 呼吸の停止: 家族など周囲の人から指摘されることが多いです。
- 息苦しさで目が覚める
- 何度もトイレに起きる(夜間頻尿)
- 寝汗をかく
日中に現れる主な症状:
- 日中の強い眠気: 会議中や運転中など、通常では眠らないような状況でも眠り込んでしまうことがあります。
- 起床時の頭痛
- 倦怠感、疲労感
- 集中力や記憶力の低下
- 気分の落ち込み、抑うつ症状
これらの症状は、睡眠の質の低下によって引き起こされます。特に日中の強い眠気は、交通事故や労働災害の原因となることもあり、注意が必要です。
III. 睡眠時無呼吸症候群の予後
睡眠時無呼吸症候群を治療せずに放置すると、体に様々な悪影響を及ぼし、生活習慣病のリスクを高めたり、生命に関わる合併症を引き起こしたりする可能性があります。
- 高血圧: SAS患者さんの約半数に高血圧が認められると言われています。睡眠中の無呼吸による低酸素状態や交感神経の亢進が原因と考えられています。
- 心血管疾患: 狭心症、心筋梗塞、不整脈(特に心房細動)、心不全などのリスクが高まります。夜間の低酸素血症や血圧の変動が心臓に負担をかけるためです。
- 脳血管障害: 脳梗塞や脳出血のリスクが上昇します。
- 糖尿病: インスリンの効きが悪くなる「インスリン抵抗性」を引き起こし、糖尿病の発症や悪化に関与すると考えられています。
- 脂質異常症(高脂血症)
- 認知機能の低下
- うつ病
- 突然死のリスク上昇
しかし、適切な治療を行うことで、これらの合併症のリスクを軽減し、QOL(生活の質)を改善することが可能です。早期発見・早期治療が非常に重要です。
Ⅳ. 睡眠時無呼吸症候群の原因(リスク因子)
睡眠時無呼吸症候群の原因は、主に気道の閉塞によるものです(閉塞性睡眠時無呼吸症候群)。
- 肥満: 首周りや喉、舌の付け根などに脂肪がつくことで気道が狭くなります。最も一般的な原因の一つです。
- 顎の骨格: 下顎が小さい(小顎症)、顎が後退している、気道がもともと細いといった骨格的な特徴も原因となります。
- 扁桃肥大・アデノイド: 特に小児のSASでは主な原因となります。成人でも見られることがあります。
- 舌が大きい(巨舌症)
- 鼻の病気: 鼻中隔弯曲症、アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎などによる鼻詰まりは、口呼吸を促し、気道を狭くする要因となります。
- 加齢: 加齢とともに喉や首周りの筋力が低下し、気道が塞がりやすくなります。
- 飲酒: アルコールは筋肉を弛緩させる作用があるため、就寝前の飲酒は気道の閉塞を悪化させます。
- 睡眠薬: 筋弛緩作用のある睡眠薬は、症状を悪化させる可能性があります。
- 喫煙: 気道の炎症を引き起こし、SASのリスクを高めます。
- 性別: 男性の方が女性よりも発症しやすい傾向にあります。女性ホルモンには気道を開存させる働きがあるためと考えられていますが、閉経後の女性はリスクが上昇します。
中枢性睡眠時無呼吸症候群の場合は、心不全、脳卒中、腎不全などの基礎疾患や、一部の薬剤が原因となることがあります。
Ⅴ. どういう人がなりやすいか
上記のリスク因子に当てはまる人は、睡眠時無呼吸症候群になりやすいと言えます。具体的には以下のような方が挙げられます。
- 肥満の方(特に首周りに脂肪が多い方)
- 顎が小さい、または後退している方
- 扁桃腺が大きい方
- 鼻炎や副鼻腔炎などで鼻詰まりがある方
- 高齢の方
- 日常的に飲酒量が多い方
- 喫煙者
- 男性(特に中年以降)
- 閉経後の女性
- 家族にいびきが大きい、または睡眠時無呼吸症候群と診断された人がいる方
- 高血圧、糖尿病、心疾患などの生活習慣病をお持ちの方
痩せている方でも、顎の骨格や扁桃肥大などが原因で発症することがあります。「太っていないから大丈夫」とは限りません。
Ⅵ. 検査方法
睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合、以下のような検査を行います。
- 問診・診察: 自覚症状や生活習慣、既往歴などを詳しく伺います。いびきの状況や睡眠中の様子をご家族から聴取することも重要です。また、喉や鼻の状態、顎の形などを診察します。
- 簡易検査(自宅でのスクリーニング検査): 手の指や鼻の下にセンサーを装着し、睡眠中の呼吸の状態、血液中の酸素飽和度、いびきの音などを記録する検査です。ご自宅で普段通りに寝ている間に行うことができます。この検査でSASの疑いが強いと判断された場合、さらに詳しい検査に進みます。 当院でもこの簡易検査の貸し出しを行っております。
- 精密検査(ポリソムノグラフィー検査:PSG): SASの確定診断や重症度を評価するために行う、より詳細な検査です。当院では専門の業者から患者様へ直接検査方法についての詳細ご説明の機会を設けさせていただきますのでご安心ください。脳波、眼球運動、心電図、筋電図、呼吸、血液中の酸素飽和度、いびき、胸部・腹部の動き、睡眠中の体位など、様々な生体情報を同時に記録します。 この検査結果(特にAHI:無呼吸低呼吸指数)に基づいて、治療方針が決定されます。
VII. 治療方法
睡眠時無呼吸症候群の治療法は、重症度や原因、患者さんの状態によって異なります。主な治療法には以下のようなものがあります。
- CPAP(シーパップ:経鼻的持続陽圧呼吸療法): 中等症から重症の閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)に対する最も効果的で標準的な治療法です。睡眠中に鼻に装着したマスクから空気を送り込み、気道が塞がるのを防ぎます。治療を開始すると、睡眠中の無呼吸やいびきが劇的に改善し、日中の眠気や倦怠感も軽減されることが多いです。健康保険が適用されます。
- マウスピース(口腔内装置): 軽症から中等症のOSASで、主に下顎が小さいなどの骨格的な問題がある場合に有効なことがあります。歯科で専用のマウスピースを作成し、睡眠中に装着することで下顎を前方に移動させ、気道を広げます。CPAPが合わない場合の代替治療としても選択されます。
- 生活習慣の改善:
- 減量: 肥満が原因の場合、減量は非常に効果的です。
- 禁酒・節酒: 特に就寝前の飲酒は避けるようにします。
- 禁煙: 喫煙は気道の炎症を引き起こし、SASを悪化させます。
- 睡眠時の体位の工夫: 横向きに寝ることで、気道の閉塞が軽減される場合があります。
- 睡眠薬の見直し: 筋弛緩作用のある睡眠薬を使用している場合は、医師に相談してください。
- 外科的手術: 扁桃肥大やアデノイドが原因の場合(特に小児)や、鼻の病気(鼻中隔弯曲症など)が原因でCPAP治療が困難な場合などに検討されることがあります。口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)などがありますが、効果や適応は慎重に判断されます。
- 中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSAS)の治療: 原因となっている基礎疾患(心不全、脳血管障害など)の治療が優先されます。ASV(Adaptive Servo-Ventilation)という特殊な人工呼吸器が用いられることもあります。
VIII. 当院の対応可否
当院では、睡眠時無呼吸症候群が疑われる患者さんに対して、まずは問診と診察を行います。その上で、ご自宅で実施可能な簡易検査機器を手配し、SASのスクリーニングを行います。
簡易検査の結果、中等症以上のSASが強く疑われる場合、さらに精密検査やCPAP治療の導入を検討していく流れとなります。
また、睡眠時無呼吸症候群は高血圧や心疾患といった循環器疾患と密接に関連しているため、当院では循環器専門医の立場から、これらの合併症の管理や予防にも力を入れています。SASの治療と並行して、循環器疾患のリスク管理を行うことが重要です。
SASの治療によって血圧が下がるケースも多く報告されており、循環器内科としてもしっかりとサポートさせていただきます。気になる症状がございましたら、お気軽にご相談ください。
Ⅸ.セルフチェック
あなたの睡眠に隠れたリスクはありませんか? ご自身の症状や、ご家族から指摘されたことを思い出しながら、当てはまる項目をチェックしてみましょう⇒こちらをチェック
Ⅹ. Q&A(よくあるご質問)
Q1. 治療はどのくらいの期間続ければ良いですか?
A1. 睡眠時無呼吸症候群は、高血圧や糖尿病のように、根本的な原因(肥満や骨格など)が解消されない限り、治療を継続する必要があります。特にCPAP療法は、対症療法であり、使用している間だけ効果が得られます。自己判断で中断せず、医師の指示に従ってください。ただし、大幅な減量に成功した場合など、状態によっては治療が不要になることもあります。
Q2. CPAP療法は一生続けなければいけませんか?
A2. 必ずしも一生とは限りませんが、多くの場合、長期的な継続が必要となります。肥満が原因でSASになっている方が大幅な減量に成功したり、他の原因が外科手術などで改善されたりした場合には、CPAP療法を離脱できる可能性もあります。定期的な評価を受け、医師と相談しながら治療方針を決定していくことが大切です。
Q3. 子供でも睡眠時無呼吸症候群になりますか?
A3. はい、お子さんでも睡眠時無呼吸症候群になることがあります。小児の場合は、アデノイド肥大や扁桃肥大が主な原因であることが多いです。いびき、陥没呼吸、お漏らし、落ち着きがない、学業不振などの症状が見られる場合は、小児科や耳鼻咽喉科にご相談ください。
Q4. 痩せれば必ず治りますか?
A4. 肥満が主な原因である場合は、減量によって症状が大幅に改善したり、治癒したりする可能性があります。実際に、体重が10%減少すると、無呼吸低呼吸指数(AHI)が約26%減少するという報告※もあります。しかし、顎の骨格など他の要因が関わっている場合は、痩せるだけでは治らないこともあります。
※引用論文:Longitudinal study of moderate weight change and sleep-disordered、 リンクbreathinghttps://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/193382#google_vignette)
Q5. いびきをかかなければ睡眠時無呼吸症候群ではないですか?
A5. いびきは睡眠時無呼吸症候群の代表的な症状の一つですが、いびきをかかないタイプのSASも存在します(特に中枢性の場合や、一部の閉塞性の場合)。また、いびきが一時的に止まっている時は、むしろ呼吸が止まっているサインである可能性もあります。日中の強い眠気など、他の症状がある場合は注意が必要です。
Q6. 日中の眠気がなければ、治療しなくても大丈夫ですか?
A6. 日中の眠気は代表的な自覚症状ですが、眠気を感じにくい方や、眠気に慣れてしまっている方もいます。眠気がなくても、睡眠中に無呼吸・低呼吸を繰り返していると、心臓や血管に負担がかかり、高血圧や心血管疾患、脳卒中などのリスクが高まります。症状だけで判断せず、気になる場合は検査を受けることをお勧めします。
Q7. CPAP療法の費用はどのくらいかかりますか?
A7. CPAP療法は健康保険が適用されます。3割負担の方の場合、月々の自己負担額は一般的に3,000~5,000円程度です(診察料、機器レンタル料などを含む)。詳細な費用については、医療機関にご確認ください。
Q8. 旅行や出張時のCPAP装置はどうすれば良いですか?
A8. CPAP装置は持ち運びが可能です。多くの機種は比較的コンパクトで、専用のキャリーバッグも用意されています。事前に航空会社に確認すれば、機内への持ち込みや使用が可能な場合もあります。長期間の旅行や海外出張などの場合は、事前に医師に相談し、指示を受けるようにしてください。バッテリー式のものや、携帯性に優れた小型の機種もあります。
Q9. どのタイミングで病院を受診すれば良いですか?
A9. 「大きないびきを指摘された」「日中、我慢できないほどの眠気がある」「寝ても疲れが取れない」「起床時に頭痛がする」などの症状が続く場合は、一度医療機関にご相談ください。特に、ご家族やパートナーから睡眠中の呼吸の停止を指摘された場合は、早めの受診をお勧めします。
Q10. 循環器内科で睡眠時無呼吸症候群の相談をしても良いのですか?
A10. はい、もちろんです。睡眠時無呼吸症候群は高血圧、心房細動、心不全といった循環器疾患の重要なリスク因子であり、合併しているケースも少なくありません。当院のような循環器内科では、SASの簡易検査の実施や、循環器疾患との関連を踏まえた総合的な健康管理のアドバイスが可能です。精密検査や専門的な治療が必要な場合は、適切な医療機関へご紹介いたします。
その他(参考リンク)
【コラム】睡眠時無呼吸症候群(SAS)と循環器疾患/糖尿病の関連について
おわりに
睡眠時無呼吸症候群は、単なるいびきや眠気の問題ではなく、全身の健康に影響を及ぼす可能性のある病気です。しかし、適切な検査と治療を行えば、症状を改善し、合併症のリスクを減らすことができます。
気になる症状がある方は、どうぞお気軽に当院にご相談ください。