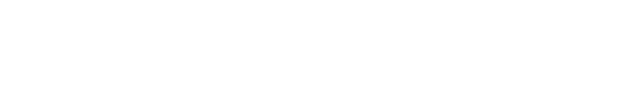糖尿病(検査)
【はじめに】
糖尿病は、自覚症状がないまま進行することが多い病気です。そのため、定期的な検査でご自身の体の状態を正確に把握し、早期発見・早期治療につなげることが非常に重要です。
このコラムでは、一般的に行われている主な糖尿病検査の内容と、その結果がどのような状態を示すのかについて、最新の情報を交えて詳しく解説します。
1.基本検査(糖尿病を診断し、血糖コントロール状態を把握する)
糖尿病の診断や治療効果の判定には、主に「血糖検査」と「ヘモグロビンA1c (HbA1c) 検査」が行われます。これらの数値を組み合わせて、総合的に評価します。
◆血糖検査
血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)を測定する検査です。測定するタイミングによって、主に3つの種類があります。
①空腹時血糖値
10時間以上食事をとらず、空腹の状態で測定する血糖値です。健康診断などでも広く行われます。
≪検査値目安≫
・正常型: 110 mg/dL 未満
・境界型(糖尿病予備群): 110~125 mg/dL。将来、糖尿病に移行するリスクが高い状態です。生活習慣の見直しが推奨されます。
・糖尿病型: 126 mg/dL 以上。糖尿病が強く疑われます。
②随時血糖値
食事の時間とは関係なく、採血した時点での血糖値です。
≪検査値目安≫
・糖尿病型: 200 mg/dL 以上。この値を示す場合、糖尿病の可能性が高まります。
③75g経口ブドウ糖負荷試験 (75gOGTT)
空腹時血糖値を測定した後、ブドウ糖液(ブドウ糖75gを溶かした水)を飲み、30分後、1時間後、2時間後などの血糖値を測定します。インスリンの分泌能力や反応性を詳しく評価できる検査です。
≪検査値目安≫
・正常型: 140 mg/dL 未満
・境界型(糖尿病予備群): 140~199 mg/dL。「かくれ糖尿病」とも呼ばれ、空腹時血糖値が正常でも、食後の血糖値が上がりやすい状態を捉えることができます。
・糖尿病型: 200 mg/dL 以上。
◆ヘモグロビンA1c (HbA1c) 検査
過去1~2ヶ月間の平均的な血糖コントロール状態を反映する重要な指標です。赤血球中のヘモグロビンに、血液中のブドウ糖がどのくらいの割合で結合しているかを示します。
≪検査値目安≫
・正常値: 5.6% 未満
・糖尿病型:6.5% 以上で「糖尿病型」と診断判定されます。
★治療目標: 治療中の方の目標値は年齢や合併症の有無などによって個別に設定されますが、一般的には合併症予防のために「7.0% 未満」を目指します。
【糖尿病の診断確定について】
糖尿病の診断は、一度の検査だけではなく、複数の検査結果を組み合わせて慎重に行われます。例えば、以下のいずれかの場合に糖尿病と診断されます。
・血糖値(空腹時、75gOGTT、随時いずれか)とHbA1cが、同日の検査でともに「糖尿病型」を示した場合。
・別々の日に検査を行い、血糖値とHbA1cがそれぞれ「糖尿病型」を示した場合。
・血糖値が「糖尿病型」を示し、口の渇き、多飲、多尿、体重減少などの典型的な症状や、確実な糖尿病網膜症が確認された場合。
2.合併症のチェックに欠かせない検査
糖尿病は、高血糖の状態が続くことで全身の血管にダメージを与え、様々な合併症を引き起こす可能性があります。そのため、定期的に以下の検査を行い、合併症の早期発見に努めます。
◆尿検査
尿中の糖(尿糖)やタンパク(尿蛋白)の有無を調べます。
≪検査値目安≫
・尿糖: 血糖値が概ね160~180 mg/dLを超えると、腎臓で糖を再吸収しきれなくなり尿中に漏れ出てきます(尿糖陽性)。高血糖状態を知る一つのサインです。
・尿蛋白(特にアルブミン尿): 糖尿病腎症の最も重要な早期発見マーカーです。
・微量アルブミン尿(30~299 mg/g・Cr): 腎症の初期段階(早期腎症期)を示します。この段階で適切な治療を行えば、正常な状態に戻る可能性があります。
・顕性アルブミン尿(300 mg/g・Cr以上): 腎症が進行した状態(顕性腎症期)です。腎機能の低下が進むため、厳格な血糖・血圧管理が不可欠です。
◆眼底検査
瞳孔を開く目薬をさし、眼の奥にある網膜の血管の状態を直接観察します(眼科医による専門的な検査)。
≪検査でわかること・異常所見≫
糖尿病網膜症の有無や進行度を評価します。「単純網膜症」「増殖前網膜症」「増殖網膜症」などの病期があり、進行すると視力低下や失明につながるため、自覚症状がなくても年1回以上の定期的な検査が強く推奨されます。
◆動脈硬化を調べる検査
高血糖は動脈硬化を促進し、心筋梗塞や脳梗塞、足の血流障害のリスクを高めます。
・頸動脈エコー検査: 首の動脈(頸動脈)の壁の厚さ(IMT)や、プラーク(血管内のこぶ)の有無を調べ、全身の動脈硬化の指標とします。IMTが1.1mmを超えると動脈硬化が進んでいると判断されます。
・ABI(足関節上腕血圧比)検査: 腕と足首の血圧を比較することで、足の血管の詰まり具合を評価します。ABIが0.9以下の場合、足の血管が狭くなったり詰まったりしている閉塞性動脈硬化症が疑われます。
・心電図検査、心エコー検査: 糖尿病による心臓への負担や、狭心症・心筋梗塞などの虚血性心疾患の兆候がないかを評価します。
◆神経伝導検査
手足の神経に微弱な電気を流し、その伝わる速度や強さを測定します。(※当院では実施していません)
≪検査でわかること・異常所見≫
糖尿病神経障害の診断に用いられます。神経の伝わる速度が遅くなるなどの異常が見られた場合、しびれや痛み、感覚の鈍麻といった症状の原因が神経障害によるものであると判断する材料になります。
【最後に】
検査結果で異常を指摘された場合は、決して自己判断せず、必ず医師にご相談ください。
たとえ「境界型」であっても、それは体からの重要なサインです。専門家のアドバイスのもと、適切な対策を講じることが、将来の健康を守るために何よりも大切です。
【疾患について】
下記当院のリンクもご参考いただけますと幸いです。